慈善なのか偽善なのか
「自分の国で苦しんでいる人がいるのに他の国の人間を助けようとする人は、他人によく思われたいだけの偽善者である」
「大切なことは、遠くにある人や、大きなことではなく、目の前にある人に対して、愛を持って接することだ」
「日本人は他国のことよりも、日本のなかで貧しい人々への配慮を優先して考えるべきです。愛はまず手近なところから始まります」
これらの言葉は、1980年代に訪日したマザー・テレサが、日本人に向けて言ったとされる言葉だ
ちょっとGoogleで調べてみれば、「マザー・テレサが実際にこの言葉を言ったかどうかは確認されていない」という検証を行なっているWebサイトを見つけることができる。
しかし、芸能人が寄付を行ったというニュースや慈善行為に関わっている有名人へのインタビュー記事などに付いたSNSのコメントを見てみると、「偽善者」に対する批判をおこなうためにこの言葉を持ち出す人は、いまだに多い。また、学生の頃にわたしが友人と会話をしているときにも、国際ボランティアサークルに入っていたり街頭で寄付活動をしていたりする学生を揶揄する文脈で、マザー・テレサの「名言」が持ち出されることがあった。
マザー・テレサは一部の人たちの間では毀誉褒貶が激しい人物であるが、世間では「善」や「愛」を体現する人物として扱われているようだ。そして、彼女の名言は、善や愛に対してわたしたちが抱いている感覚を見事に表現した言葉であるように思える。大半の人は、「愛は近くの人に対して向けるべきであり、遠くの人ばかりを気にかける人間が善い人間であるはずがない」と感じている。本人が言っていない可能性の高いセリフがここまで多くの人の印象に残って引用され続けているのは、その言葉が、善や愛に関する真実の一端を突いているように感じられるからこそだろう。
「かわいそうランキング」というマジックワード
わたしたちは他人の「偽善」を非難するのが大好きだ。マザー・テレサの名言を持ち出さなくとも、慈善行為や寄付を行っている人に対する批判の言葉には事欠かない。
たとえば、日本のインターネットには「かわいそうランキング」という言葉がある。これは、「弱者を助けようと思っている人は、"どんな弱者から助けるか"という優先順位を決めるときに、自分が"かわいそう"だと思う弱者から優先して助けてしまい、"かわいそう"に思えない弱者を後回しにしたり無視したりする」という現象を指し示す言葉である。
ほとんどの場合、「かわいそうランキング」という言葉は、他人を批判する文脈で持ち出される。この言葉を使っている人たちは、「壮年や中年よりも子供や高齢者の方が、男性よりも女性の方が、日本人よりも外国人の方が、マジョリティよりもマイノリティの方が救済される優先順位が高い」と考えていて、それに対する抗議や批判を行なっているのだ。
逆に言うと、「かわいそうランキング」という言葉を使う人の大半は、日本人の壮年・中年男性であるようだ。彼らは、自分たちの属性が世間から冷遇されて救済の対象にもならないことへの怒りや抗議の意思を、「かわいそうランキング」という言葉に込めているのである。
たしかに、個人による寄付や慈善行為に限定すると、「かわいそう」という感情やそれに類する感情が寄付や慈善の対象や量を決める判断に影響を生じさせることは、心理学の研究によっても確認されている事実ではある。
たとえば、ある人が救済の対象を決める判断を行う際には「特定可能な被害者」と呼ばれるバイアスがはたらくことが、心理学の実験によって明らかになっている。
倫理学者のピーター・シンガーの著書『あなたが救える命:世界の貧困を終わらせるために今すぐできること』から引用しよう(奇遇なことに、ここでもマザー・テレサの言葉が出てくることになる……ただし、こんどの言葉は彼女が実際に言ったものだ)。
気前のよい寄付はどのような要因によって生み出されるかを調べようとした研究者たちがいる。彼らはある心理学の実験において、研究参加者にお金を渡し、その一部をセーブ・ザ・チルドレンという米国や途上国の貧しい子どもたちの支援を行なっている団体に寄付する機会を与えた。第一のグループには、寄付の必要性について一般的な情報が与えられた。一般的な情報とは「マラウイでは食糧不足によって三〇〇万人以上の子どもが影響を受けています」という類いのものである。第二のグループには、マラウイに住むロキアという名前の七歳の女の子の写真が示された。そして、ロキアは極度に貧しいことと、「彼女の人生はあなたの寄付によってよい方へと変わります」ということが彼らに伝えられた。
ロキアの情報を与えられたグループは、一般的な情報しか与えられなかったグループよりも、寄付額が有意に大きかった。次に、第三のグループには一般的な情報とロキアの写真およびロキアについての情報が与えられた。そのグループの寄付額は一般的な情報しか与えられなかったグループよりも大きかったが、それでもロキアについての情報のみを与えられたグループよりは小さかった。さらに、ロキアの情報に加えて──一般的な情報は与えずに──もう一人の子どもの情報を与えた場合でさえ、一人の子どもについてのみ述べた場合よりも、平均の寄付額は低くなった。この実験の参加者たちは、二人の子どもの場合よりも一人の子どもについて情報を与えられたときの方が、強い感情を抱いたと確信した。
(……中略……)
この分野の第一人者であるポール・スロヴィックの考えでは、「特定可能な人」が──さらに言えば、すでに選ばれた人というだけでも──私たちにこれほど大きく訴えかけるのは、私たちが情動システムと熟慮システムという二つの異なるプロセスを用いて現実を把握し、何をするべきかを決めているためである。
(……中略……)
助けを必要としている人は、私たちの感情を強くゆさぶる。これは私たちの情動システムが作用しているためだ。マザー・テレサの次の言葉はこのことを言い表している。「群衆を目にしても私は決して助けようとしません。それが一人であれば、私は助けようとします」。もし立ち止まってよく考えてみれば、「群衆」とは人々の集まりのことであり、その個々の人は「一人」の人と同じくらい助けを必要としていることが、私たちにはわかる。そして、合理的に考えるならば、ただ一人を助けるよりも、そのひとに加えて別の人も助けた方がよく、またその二人に加えてもう一人を助けたほうがさらによい等々ということがわかる。私たちは自分の熟慮システムが正しいことを知っているが、マザー・テレサにとっても他の多くの人にとっても、助けを求める一人の人が持つ私たちの感情を強くゆさぶる要素がこの知識には欠けているのである。
(シンガー、 p.59-61)
要するに、わたしたちは一人の困っている少女の具体的なイメージを示されると「かわいそう」と感じて、寄付などの行動を実行しやすくなるが、困っている人がたくさんいることを統計や数字で示されても「かわいそう」という感情が湧かないから行動を実行しづらい、ということだ。
また、「かわいそう」という感情がはたらくかどうかは、対象となる相手の属性にも影響される。
自然保護団体が野生動物や生態系の保護のために寄付キャンペーンを行うときには、クジラやトラやホッキョクグマなどの哺乳類動物をキャンペーンのアイコンとしたほうが、ヘビやカエルやクモなどをアイコンにするよりも、寄付金がずっと集まりやすい。わたしたち人間は自分と同じ哺乳類たちには共感することができて「かわいそう」という感情を抱くことが容易であるが、爬虫類や両生類や節足動物に共感することは困難であるためだ。
さらに、犯罪や紛争による犠牲者は概して男性の方が多いが、女性の犠牲の方が問題視されて取り上げられやすい、という性別バイアスの問題もよく指摘されることである。
非合理性をあげつらい、バカにする
「特定可能な被害者」効果や、哺乳類動物や女性を優先するバイアスのことを考慮すると、「弱者を救済しようとしたときに感情に基づいた判断をしてしまうと、救済の対象が不公平で不合理なかたちで選ばれてしまう」という「かわいそうランキング」批判者たちの主張は、それ自体は正しいと言えるだろう。
とはいえ、マザー・テレサの名言と「かわいそうランキング」批判には通底する心情があることを見逃してはならない。慈善を行なっている人の「偽善」や「非合理性」をあげつらい、批判したりバカにしたりするという点で、この二つは共通しているのだ。
「かわいそうランキング」批判者は、海外の貧困問題や災害による犠牲者に心を痛めて慈善行為や寄付を行おうとする人に対しても批判の矛先を向けることが多い。国内で起こっている貧困問題により同胞が苦しんでいることを無視して、縁もゆかりもない人が海外で苦しんでいることの方に関心を向けることも、「かわいそう」という感情に支配された非合理的な判断である、と彼らは主張する。
先述したように、「かわいそうランキング」という言葉を用いて批判を行う人の大半は、日本人の男性だ。多かれ少なかれ、彼らは自分たち自身のことを弱者であると見なしている。そのため、彼らの主張には「"わかりやすい"弱者たちを救済するために向けられている情熱や資源は、自分たちのような"わかりにくい"弱者の救済にも向けられるべきだ」という本音が見え隠れする。……もっとも、「かわいそうランキング」批判者のなかには、ロスジェネ世代の中年男性をはじめとして、日本社会のなかでは経済的に苦しい状態で生きており、福祉政策や経済政策などによる救済の対象から外れがちな人も、多く含まれているようだ。そんな彼らが「自分たちは日本社会から見捨てられて、助けてもらえなかった」という怒りや被害者意識を抱くことには、無理からぬ側面もある。
だが、自国内の弱者ではなく国外の弱者を救おうとする人たちのことを不愉快に思い、 そのような人たちを批判したり揶揄したりしたいと思っている人は、「かわいそうランキング」批判者に限らない。かなり多くの人が、自分自身は比較的恵まれており救済を必要としてない状態であっても、寄付や募金、国際ボランティアサークルや慈善団体に対して否定的なイメージを持っているのだ。だからこそ、自分がよく思っていない相手のことを「偽善者」だと非難するマザー・テレサの名言が人口に膾炙したのである。
バイアスをすべて排除したとしても
マザー・テレサの名言は「自分の国で苦しんでいる人」と「他の国の人間」との比較から始まり、「愛はまず手近なところから始まります」という言葉で終わる。また、「かわいそうランキング」批判者たちも「国内の弱者たちから救済するべきだ」と主張する。
ここで、ちょっと立ち止まってほしい。
言うまでもなく、「愛」は感情だ。それに、自分の国で苦しんでいる人を他の国の人間よりも優先することが善いことであり、合理的なことであるとは、まだ決まっていない。たしかに、「特定可能な被害者」や「わかりやすい属性の弱者」ばかりを優先することは、バイアスのかかった判断であるだろう。……しかし、それと同じように、自分の国で苦しんでいる人を他の国で苦しんでいる人より優先することも、バイアスがかかった判断であるかもしれない。
先ほど、「特定可能な被害者」効果を紹介するためにシンガーの『あなたが救える命:世界の貧困を終わらせるために今すぐできること』を紹介した。しかし、この本のタイトルが示唆しているように、シンガーは寄付や慈善行為を批判しているのどころか推奨しているのだ。
「特定可能な被害者」効果について論じられているのは、「人を寄付から遠ざける心理的なバイアスとはなにか?」ということについて考察している章のなかである。そして、同じ章のなかでは、「身近な人をひいきすること」も心理的なバイアスの一種として論じられている。
たとえ私たちが気前よく寄付する場合でも、自国内の人々を助ける場合に比べて、外国の人々を助ける際には、私たちが寄付する額ははるかに少ない。二〇〇四年のクリスマス直後に東南アジアを襲った津波は二十二万人の犠牲者を出し、何百万人もの人々が家を失い、困窮状態に陥った。アメリカ人は災害支援のために十五億四〇〇〇万ドルの寄付を行った。これはアメリカ人が国外で起きた自然災害の発生時に寄付した額としては過去最大だった。しかし、この額はアメリカ人がその翌年にハリケーン・カトリーナの被災者を助けるために寄付した六五億ドルと比べると、その四分の一以下だった。だが、ハリケーン・カトリーナによる犠牲者は役一六〇〇人であり、家を失った人々の数は二〇〇四年の津波災害に比べてはるかに少なかったのだ。
(……中略……)
このように外国人に対する関心が比較的低いことに私たちは戸惑いを覚えるかもしれない。だが、なぜ私たちがこのような傾向を持つのかを理解するのは難しいことではない。私たち人類は、親が何年にもわたって子の世話をしなければならない社会的な哺乳類として、何百万年ものあいだ進化を遂げてきた。その何百万年もの期間の大半において、こうした依存期間中に子どもの世話をしなかった親の遺伝子は、次世代に伝えられる可能性が低かった。他人の幸福に関する私たちの関心が自分の親族、自分と協力関係にある人々、またおそらくは自分が属する小さな部族集団のメンバーに限られる傾向にあるのは、その結果なのだ。
(……中略……)
遠くに住む人々への私たちの共感能力に限界があることについてアダム・スミスが記したとき、彼はこの事態は「自然が作った賢明な秩序だと思われる」と述べた。というのは、遠くに住む人々は「私たちが益することも害することもできない」人々だからである。たとえ私たちが遠くに住む人々を今以上に気にかけたとしても、「私たちの余計な心配が増えるだけで、彼らにとっては何ら利益にならない」だろう。今日、これらの言葉はスミスが本を書くのに使った羽ペンと同じくらい廃れてしまっている。津波に対する私たちの反応が生々しく示しているように、今日の高速な通信手段と輸送手段をもってすれば、スミスの時代には不可能であった仕方で遠くに住む人々を助けることができるのだ。そればかりか、先進国に住む人々と途上国に住む人々の生活水準の格差は桁外れに広がったため、先進国に住む人々が遠くに住む人々を助ける能力は以前より大きくなり、また私たちの援助を彼らに集中させる理由も以前より大きくなっている。現在では、極度の貧困状態にある人の圧倒的多数が私たちから遠く離れたところに住んでいるからだ。
(シンガー、p.65-67)
自分が思っていることや感じていることを肯定する言説は、「正しい」ものであるかのように受け止められがちだ。マザー・テレサの名言が正しいように聞こえるのは、それが「身近な人のことをひいきする」というわたしたちのバイアスを肯定する言葉であるからだろう。
そして、「かわいそうランキング」批判者の矛盾は、他人が抱いているバイアスの一部(「特定可能な被害者」効果や、哺乳類や女性を優先するバイアスなど)を選択的に非難しておきながら、「身近な人のことをひいきする」というバイアスは不問に付していることにある。この矛盾は、「かわいそうランキング」批判者の本音が「自分たちを救え」というところにある以上、必然的に生じてしまうものだ。たしかに、現状では、たとえば日本国内の中年男性は「かわいそう」に類する感情的なバイアスによって救済の対象から外されることが多いかもしれない。しかし、すべてのバイアスを排して合理的に考えたとしても、やはり、彼らに対する救済は後回しにされるべきであると判断される可能性は高いのだ。
「池で溺れている子ども」の思考実験
ほんとうの意味で「合理的」に考えるなら、わたしたちは外国で苦しんでいる人たちのことを自分の国で苦しんでいる人たちのことと同じように気にかけるべきである、とシンガーは説く。
1972年にシンガーが発表した「飢えと豊かさと道徳」という論文は、「豊かな国に住む裕福な人たちには、貧しい国で苦しんでいる人たちを救う義務がある」という考え方を哲学的に正当化する議論を行ったものだ。この論文は、発表から50年近く経った現在になっても、寄付や慈善行為に関する議論で参照されつづけている。
「飢えと豊かさと道徳」における議論は、「池で溺れている子ども」の思考実験に基づきながら展開する。
仕事に行く途中、あなたは小さな池の側を通り過ぎる。その池は膝下くらいの深さしかなく、暑い日にはときどき子どもが遊んでいる。しかし今日は気温が低く、まだ朝も早いため、あなたは子どもが一人で池の中でばしゃばしゃしているのを見て驚く。近づいてみると、その子はとても幼く、ほんのよちよち歩きで、腕をばたばたさせており、まっすぐ立つことも、池から出ることもできないでいるのだとわかった。その子の両親やベビーシッターがいないかと見回すが、辺りには誰もいない。その子どもは数秒間しか水から顔を出すことができない。あなたが池の中に入ってその子を救い出さなければ、溺れて死んでしまいそうである。池に入ることは簡単で危険ではないが、数日前に買ったばかりの新しい靴が台無しになり、スーツは濡れて泥だらけになるだろう。また、その子を救い出して保護者に預け、服を着替え終わった頃には仕事に遅刻してしまうだろう。あなたはどうすべきだろうか。
(シンガー、p.3-4)
ふつうの人であれば、たとえ自分の靴やスーツが台無しになり、それにかけた数千円や数万円の代金が無駄になるとしても、「子どもを助けるべきである」と判断するだろう。相手が余所の家庭の子どもであり、縁もゆかりもない他人であったとしても、数千円や数万円を惜しんで死にかけている人を見殺しにすることは非人道的である、と大半の人は判断するはずだ。
また、池の位置は自分が歩いている道のすぐ側にはなく、道の向こう側にあったとしても、子どもが溺れかけているという事態に気が付いたら道路の向こう側にまで行って助けるべきである、と大半の人が判断するだろう。池がすぐ側にあるか向こう側にあるかという「距離」の要素は、子どもを助けるべきか否かという道徳的な判断にはなんら関係がないからだ。
そして、余所の家庭の子どもであっても助けるべきであるなら、外国の子どもも助けるべきである。子どもの命を救うためには靴やスーツが濡れて台無しになることも許容しなければならないとしたら、新品のスーツや靴を買うことを諦めてその分のお金を子どもの命を救うために使うことも、許容しなければならない。子どもが道路の向こう側にいるとしても助けるべきであるとしたら、子どもが地球の裏側にいるとしても助けるべきであるはずだ。……とすれば、靴やスーツに使うぶんのお金を援助団体に寄付することで外国の子どもの命が救えるのであれば、わたしたちは援助団体に寄付をするべきなのだ。
「池で溺れている子ども」の思考実験では救済の対象が子どもとされているごとから、「結局、その判断も"かわいそう"という感情に基づいているのではないか」と批判する人もいるかもしれない。しかし、「わたしたちには援助団体に寄付する義務がある」という主張は、ごく論理的なかたちに整理することができる。
第一の前提 食料、住居、医療の不足から苦しむことや亡くなることは、悪いことである。
第二の前提 もしあなたが何か悪いことが生じるのを防ぐことができ、しかもほぼ同じくらい重要な何かを犠牲にすることなくそうすることができるのであれば、そのように行為しないことは間違っている。
第三の前提 あなたは援助団体に寄付することで、食料、住居、医療の不足からの苦しみや死を防ぐことができ、しかも同じくらい重要な何かを犠牲にすることもない。
結論 したがって、援助団体に寄付しなければ、あなたは間違ったことをしている。
(シンガー、p.18-19)
「効果的な利他主義」の提唱
シンガーは「池で溺れている子ども」の思考実験に基づいて国際援助や寄付の義務を立証した一方で、「最大多数の最大幸福」を重視する功利主義も主張している。
この二つを結び付けることで登場したのが、「効果的な利他主義」運動だ。この名称が生み出されたのは2000年代の後半であるが、運動が活発化したのは2010年代からである。現在では、ビル・ゲイツやウォーレン・バフェットのような億万長者も効果的な利他主義に賛同して、多額の寄付を行なっている。
この運動の根幹となる考え方について、シンガーと同じく功利主義を主張する哲学者であるウィリアム・マッカスキルの著書『〈効果的な利他主義〉宣言!──慈善活動への科学的アプローチ』から引用しよう。
効果的な利他主義で肝要なのは、「どうすれば最大限の影響を及ぼせるか?」と問い、客観的な証拠と入念な推論を頼りに、その答えを導き出そうとすることだ。いわば慈善活動に対して科学的なアプローチを取り入れるわけだ。何が真実なのかを素直で中立的な視点から突き詰め、それがどういう真実であろうと真実だけを信じると誓うのが「科学」であるとするなら、何が世界にとって最善なのかを素直で中立的な視点から突き詰め、それがどういう行動であろうと最善の行動だけを取ると誓うのが「効果的な利他主義」なのだ。
その言葉が示す通り、「効果的な利他主義」は「効果的」と「利他主義」というふたつの要素からなる。ここで、それぞれの要素の意味を明確にしておきたい。私が使う「利他主義」という言葉は、単純にほかの人々の生活を向上させるという意味だ。利他主義には自己犠牲がつきものだと考える人々も多いけれど、自分自身の快適な生活を維持しつつ相手にとってよいことができるなら、それに越したことはない。私はそれを喜んで利他主義と呼ぼう。もうひとつの要素は「効果的」という部分だ。これは手持ちの資源でできるかぎりのよいことを行うという意味だ。効果的な利他主義では、単に世界をよりよくするとか、ある程度よいことを行うのではなく、できるかぎりの影響を及ぼうとする。
(マッカスキル、p.13)
効果的な利他主義の考え方に基づき、手持ちの資源でできるかぎりのよい影響を及ぼそうとすると、マザー・テレサの名言とは全く真逆の主張が導かれることになる。「富裕国の人であれば、自国のなかで貧しい人々のことよりも、他国(貧困国)の人々への配慮を優先して考えなければならない」のだ。さらに、「外の国で苦しんでいる人がいるのに自分の国の人間を助けようとする人は、他人(身内びいきのバイアスがかかった人)によく思われたいだけの偽善者である」と言うことができるかもしれない。
収穫逓減の法則
日本やアメリカのような富裕国に暮らしている人は自国の内部にいる貧困層よりも貧困国に暮らす最貧困層の人々の救済を優先すべき理由のひとつが、「収穫逓減の法則」だ。簡単に言ってしまうと、インプットの量が同じである場合には、インプットの対象となるものの元からの状態の差によって、インプットから得られる価値に差が生じる、という法則である。たとえば、10万円しか持たない人がさらに10万円を得る場合にその人が感じる価値と、すでに100万持っている人がさらに10万円を得る場合にその人が感じる価値を比較した場合、単純に考えると前者は後者の10倍の価値を感じることになるはずだ。
収穫逓減の法則が富裕国よりも貧困国への援助を優先する根拠となることについて、マッカスキルは富裕国と貧困国のそれぞれにおいて失明の問題に対処する場合のコストパフォーマンスの差を例にとりながら、説明している。
たとえば、5万ドルあれば、1頭の盲導犬を訓練し、目の見えない人に提供できる。当然、その人の生活の質は大きく向上するだろう。しかし、同じ5万ドルで失明を完全に治せるとしたら、そのほうがより効果的なお金の使い方といえる。同じコストでより大きな便益をもたらせるからだ。5万ドルあれば、発展途上国のひとりに失明治療を施せるだけではない。トラコーマ(細菌感染によってまぶたが内側にまくれこみ、まつ毛が常に角膜を引っ掻く状態になる)の患者に失明を予防する手術を行えば、500人を失明から救うことができる。富裕国に100ドルで失明治療ができる医療プログラムがあれば、とっくに十分な補助がされているだろう。しかし、貧困国ではちがう。つまり、私たちは国内よりも貧困国の人々に対してのほうがずっと大きな貢献ができるのだ。
(マッカスキル、p.63-64)
また、マッカスキルによると、アメリカ人の平均的な労働者は、世界の最貧困層よりも100倍の所得を得ている。この「100倍」とは、各国における物価の差を織り込んだうえで100倍、ということだ。そのため、「貧困国では物価が安いから、少ない所得でも富裕国と同程度の豊かな生活ができる」ということにはならない。
マッカスキルの著書で参照されているデータは2014年のものであるが、それによると、地球上で12億2000万人が1日あたりの所得が1・5ドルを下回っていたのである。ここでいう「1・5ドル」も、各国ごとの物価の差を調整したうえで1・5ドル、ということだ。
ここまで聞くと、不思議に思うかもしれない。なぜそんなに少ない収入で生きていけるのか?死んでしまうのでは?そう、だから現に死んでいる。少なくとも、先進国の人々よりはずっと高い頻度で。発展途上国の平均寿命が過去数十年間で急上昇したのは事実だが、サハラ以南のアフリカの貧困国の平均寿命は、アメリカの78歳ちょっとに対し、いまだ56歳に止まっている。その他の面でも、彼らの生活はその収入から想像するとおり厳しい。では、極度の貧困層の生活とはどういうものなのか?その全体像を理解すべく、マサチューセッツ工科大学の経済学者アビジット・バナジーとエステル・デュフロは、13カ国以上を対象に調査を行なった。その結果、極度の貧困にある人々は収入の大部分を食べ物に費やしながら、1日あたり平均1400キロカロリーしか摂取していないことがわかった。これは体をよく動かす男性、体を非常によく動かす女性に推奨される量の約半分だ。大多数の人々は痩せていて貧血持ちだし、大半の家庭には電気、トイレ、水道がない(ラジオはあるが)。椅子またはテーブルがある家庭でさえ1割に満たない。
(マッカスキル、p.21)
OECD(経済協力開発機構)が発表した2019年度の世界平均賃金ランキングによると、単純な平均年収のランキングでは、日本は世界で25位であった[1]。あくまで平均値であり、年収の中間値を見た場合には格差の激しいアメリカなどの国のランキングが下がるかもしれないが、それにしても、日本は先進国のなかでは一般的な労働者の収入が低い国になっていることには変わりはない。
……とはいえ、あくまで「先進国のなかでは」だ。世界には190以上の国があり、そのなかには貧困国も多く含まれている。だから、マッカスキルがアメリカ国民について行なっている議論は、多かれ少なかれ、日本にも当てはまるはずなのだ。
二つの問題への対応は両立できる
もちろん、日本国内における貧困の問題が無視されるべきではない。OECD(経済協力開発機構)の統計によると、2017年における日本の相対的貧困率は約16%であり、先進国主要7カ国(G7)のなかではアメリカに次いで二番目に高い[2]。相対的貧困の有り様は、バナジーやデュフロが描写したような「極度の貧困」とは勝手が異なるだろうが、それでも深刻な問題であることに変わりはない。
また、外国における絶対的貧困の問題を強調することには、「日本における貧困は外国に比べるとまだまだマシであるのだから、日本国内の貧困は大した問題ではなく、気にしなくていい」という主張であると捉えられてしまうリスクがある(実際に、そのような主張をする人も多くいる)。わたしがここで主張したいのは、効果の観点から言えば、個人が行う寄付や慈善行為は貧困国の絶対的貧困を減らすことに向けられるのが最もよい、ということに過ぎない。この主張と、日本は経済政策や福祉政策などを通じて国内の貧困にもっと積極的な対処を行うべきである、といった主張は両立させることができる。
また、世界における絶対的貧困の割合は1990年から2015年の間に36%から10%に減少してきた(さらに、2015年から2017年の間にも、5200万人が貧困から脱出している)[3]。そして、同じ1990年から2015年の間に、日本の相対的貧困は2%ほど上昇してきたのだ。そのため、「これからは、日本における貧困の方が重大な問題となる」と捉えている人もいることだろう。
……だが、世界銀行は、コロナウイルスの流行に伴う経済不況の影響により、2020年から2021年にかけて最大で1億5000万人が絶対的貧困に陥る、との予測を発表した[4]。世界銀行によると、貧困国だけでなく、中所得国のなかでも絶対的貧困が増えることが予測される。合計すると、最大で7億人以上の人々が、絶対的貧困に苦しむことになるのだ[5]。そして、国内の貧困について考えるときには、「特定可能な被害者」効果や「身内びいき」などのバイアスの影響もあって、わたしたちは国外にいる7億人のことをついつい忘れてしまいがちである。
マザー・テレサの名言に出てくる「他の国の人間を助けようとする人」とは、その7億人を助けようとしている人々のことである。彼らのことを「偽善者」であるとは、わたしにはとても言えない。そして、「かわいそうランキング」の批判者たちは、他人の感情やバイアスを責める前に、その感情やバイアスによって自分が救済の対象になっている可能性について考えてみるべきだろう。感情やバイアスを排して合理的に考えた場合にこそ、外国の7億人よりも彼らを優先して救済する理由はなくなってしまうかもしれないからだ。
<参考文献>
ピーター・シンガー(著)、児玉聡、石川涼子(訳)、『あなたが救える命: 世界の貧困を終わらせるために今すぐできること 』、2014、勁草書房。
ウィリアム・マッカスキル(著)、千葉 敏生(訳)、『〈効果的な利他主義〉宣言! ――慈善活動への科学的アプローチ』、2018、みすず書房。
[1] https://data.oecd.org/earnwage/average-wages.htm
[2] https://data.oecd.org/inequality/poverty-rate.htm
[3] https://data.worldbank.org/topic/11
[4] https://www.worldbank.org/ja/news/press-release/2020/10/07/covid-19-to-add-as-many-as-150-million-extreme-poor-by-2021
[5] https://mainichi.jp/articles/20201007/k00/00m/030/256000c


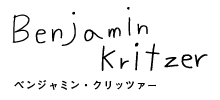 1989年生まれ。批評家。立命館大学文学部英米文学専攻卒業(学士)、同志社大学グローバル・スタディーズ研究科卒業(修士)。
1989年生まれ。批評家。立命館大学文学部英米文学専攻卒業(学士)、同志社大学グローバル・スタディーズ研究科卒業(修士)。