東京に来て何年たっただろうか、ライブの帰り道、降り注ぐ雪で慎重に徐行する真夜中の車の中でぼんやりと考えていた。
「僕たちの住んでいる街の歌です。」今日のライブのMCで自然とそんな言葉が口から出るくらいにはこの街はわたしの街と呼べるものになっているのだろう。

年の瀬ということでおきまりの今年のベストDISKなんかの選出のオファーをいくつかの媒体でもらうが、困ってしまって全て一斉に断りのメールを入れる。一年のことをまるっと思い出すことはそんなにたやすいことではない。
わたしはメールを打った人差し指で曇る窓ガラスにデタラメな落書きをしながら、つられるように一年を振り返っていた。
今年は年初にわたしのソロアルバムを連続で二枚出した。『不完全なけもの』と『やさしい哺乳類』。
平成の終わりに駆け込むように、その区切りをきっかけにして作った。未来と呼ばれる時間に飛び込むにあたってまっさらでいたかったのだ。
令和という歯がゆく聞きなれなかった年号は今では馴染みあるものになり、平和と語感の似たその時代は果たして、誰にとって平和であり、誰に対してやさしい時代なのだろうか。
目を閉じると好きな人が泣いている横顔が浮かんだりする。
個人の大きな挑戦といえば小説『銀河で一番静かな革命』を出版したことだろう。
文章を常に書くことは境界がなくだらしのないわたしの日々に新鮮なループを作った。わたしは書きながら自分ではない別の人生を体験させてもらった。
わたしがペン先で描いた人生には、ちょうどこの年の瀬の時間が流れている。
いろは、ましろは元気にしてるだろうか?神泉駅から渋谷に向かう時、どこかで彼女の背中を探している自分がいた。
そして神谷亮佑監督の『Tribe Called Discord』がスペースシャワー配給で映画化された。エンドロールに名前があった。とてもドキドキした。
何より、大阪時代から自分たちにずっとついてカメラをまわしていた神谷がやっと自分の名義で舞台に上がり、堂々と監督として挨拶している姿を誇らしく思った。偽物だったものが本物になっていく過程をこの目で見たのだ。それは喜び以外の何物でもない。
あいつの旅はまだ始まったばかりだ。無論、わたしたちも。
バンドとしてはフジロックのホワイトステージで演奏したことは、バンド史なるものがあるなら確実に刻まれた一日だっただろう。
事務所もマネージャーもいない我々が、権力のある誰かに与えてもらったものではなく真っ当なプロセスであの場所に立てたことは何よりのギフトだった。 誇りを持って日々を戦っていればどこかの道に繋がっていると証明された。
卑屈になることが簡単な時代に、できすぎた少年漫画のように真っ直ぐに信じることができたのは何よりの贈り物として自分たちの背筋を伸ばした。
そしてそれを実現させているのは間違いなく各々のフィールドにいる人たちのオルタナティブな存在に対する良心だ。
時代とは人のことだろう。
これからも出会うであろうどんな困難も目を逸らすことなく真っ向に向き合えばいいのだと背中を押された。
そして、その困難は想像よりも早くにわたしの目の前に、分厚い壁になって立ちはだかる。
全感覚祭19。一言でいえば波乱。近隣店で出た食中毒騒ぎの大阪に、台風直撃の東京、もはや示し合わされたとしか思えないようなドキュメントの到来にわたしの中での核と呼ぶべき信念、その周りをまとっていたモヤが晴れていくのを感じていた。
何を大切にしていくべきか?
それは周囲の人の行動にも如実に現れていった。表現とは、食とは。自分と他人、社会とファミリー。
各々が各々の生きてきた角度からそのことを問われ、答えを行動にかえながらわたしたちの近くにいてくれた。
人と人はどうして出会うのだろうか。そんなことを考えたくなるほどにわたしには眩しい出会いたちだった。
時代とは人だ。
笛を吹き続け警棒を振ってくれたスタッフや、草むしりのあと台風による中止に一緒に泣いてくれた人、ただご飯をおいしそうに食べてたおっさん、崩れた体調を心配してくれた友人や、同じ狂乱の日々を駆けたアーティスト、雨に飛ばされないように会場を一晩中見張ってくれたボランティア、4トントラックでスピーカーを運び、中止の知らせで京都までとんぼ返りした仲間、雨の降る日も風の強い日も体を張って育ててくれた食物を提供してくれた農家さん、その泥だらけの服や手の綺麗な皺や、それを料理し振る舞ってくれた出店店舗、そしてそこに居合わせて全感覚祭が続いていく価値があると評価してくれたあなた。
やさしい哺乳類に不完全なけもの。
その顔たちが時代でなくて何が時代だっていうのか。
どこぞのVIP ROOMでふんぞり返ってマスゲームのようにカルチャーを動かし儲けた金でシャンパンを開けてる、そこでグラス越しに語られる時代に何の価値があるのだろうか。
全感覚祭とは、祭としてただ楽しい一日を創造する以前に、庭の外の他人と関わる中で人間や時代、そして自分自身のことを理解していく、そんなプロセスなのだと思う。
まだこの世界を最低だと切り捨てないだけの良心を残してくれた2019年のあなたに感謝している。
まだわたしもあなたもやれるはずなんだ。
だって時代とはわたしやあなたのことなのだともう知っているのだから。
今年も終わろうとしている。
2020年はもうすぐそばで闇をちらつかせ、わたしは緊張している。
どんな一年になるのか?
考えれば不安になるようなことで山積みだ。政治のこと、オリンピック、移民にレイシズム、原発に地球温暖化。アフガニスタンで殺された医師の中村哲さんのことを考えると胸の奥がズキズキと痛み何一つ言葉にできない。
トピックとしてあげることが不可能なくらい数多の問題は目の前で音速で駆け巡り絡みあい、その糸はもつれ合ってる。
そんな中で、わたしは誰もが来年こそいい年にしたいと望んでいる、その一点だけで出会えないだろうかと夢想している。
神社でお賽銭箱に小銭を投げ入れ、祈る。手と手が合わされているその触れ合う一点。そこに希望がすんでいるのではないか。

何を甘ったるいことを言ってるの?夢想家の戯言と言って笑う?
だけど音楽の現場でそれを可能にしているところを何度も見てきたよ。
それは勘違いのような一瞬かもしれないが孤独のまま連帯している瞬間は確かに訪れる。主義も主張も当然差別も超えてただ、同じ音の下で酔いしれる。
それはもう平和という言葉を適応するのがふさわしく思う。
わたしたちはこれらすべての活動の裏で5枚目のアルバムを作ってきた。『狂』というアルバムだ。
2020年、この円盤を武器にどうやってサバイブしていくべきか。
ただのミュートで抑えの効かない騒音がサイレンのようにけたたましくなるところが想像できる。そして、その先でちゃんと笑えないと嘘なのだと思う。
年の瀬、やり残したことはなく、なんて言われるけど、到底そんなことは無理だろう。
これから、いちいち「2019年最後の~」なんてフレーズが蔓延するのを目の当たりにする。そう言えば「平成最後の~」なんて言葉は何度も聞いた。
だけど知っている。わたしたちは何も変われず、この街も何も変われずに2020年もそこにあり続けることを。
だらだらとだらしなく、過去を引きずり、言えなかった言葉も会えなくなった人もその影を後ろに連れて、曖昧なまま、あいも変わらずわたしのままで年をまたぐ。
かわれないのか、かわらないのか。 だけど抵抗は許されてる。
想像して。
そして懐かしい未来で会いましょう。どんな困難が待ち受けていても、きっといい年になるよ。
そう信じてる。
良いお年を。

Back Number
- 第21回 WISH 2023-12-24
- 第20回 Million Wish 2023-07-26
- 第19回 インドの灼熱、立体の祈り 2023-06-09
- 第18回 阿寒ユーカラ ウタサ祭り 2023-02-09
- 第17回 作ることの喜び、背負うことの怖さ 2022-11-15
- 第16回 真夏のピークが去った 2022-09-01
- 第15回 三月のこと 2022-03-31
- 第14回 フジロック2021 2021-08-18
- 第13回 i aiの夏 2021-07-19
- 第12回 十三月農園と種苗法 2020-10-05
- 第11回 難波ベアーズ 2020-04-09
- 第10回 静かすぎる日々 2020-04-01
- 第9回 ウタサ祭り 2020-02-19
- 第8回 東京 2020-01-12
- 第7回 2019年 2019-12-28
- 第6回 SHIBUYA全感覚祭 2019-10-28
- 第5回 Human Rebellion 2019-10-11
- 第4回 全感覚祭 大阪 2019-10-05
- 第3回 祭の前夜 2019-09-20
- 第2回 whose food? 2019-09-12
- 第1回 Future Values 2019-08-27
- 第0回 statement food 2019-08-27
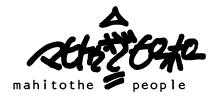 2009年、バンドGEZANを大阪にて結成。作詞作曲をおこないボーカルとして音楽活動開始。うたを軸にしたソロでの活動の他に、青葉市子とのNUUAMMとして複数のアルバムを制作。映画の劇伴やCM音楽も手がけ、また音楽以外の分野では国内外のアーティストを自身のレーベル十三月でリリースや、フリーフェスである「全感覚祭」を主催。中国の写真家Ren Hangのモデルをつとめたりと、独自のレイヤーで時代をまたぎ、カルチャーをつむいでいる。2019年、はじめての小説『銀河で一番静かな革命』(幻冬舎)を出版。GEZANのドキュメンタリー映画「Tribe Called Discord」がSPACE SHOWER FILM配給で全国上映。バンドとしてはFUJI ROCK FESTIVALのWHITE STAGEに出演。2020年、5th ALBUM「狂(KLUE)」をリリース、豊田利晃監督の劇映画「破壊の日」に出演。初のエッセイ集『ひかりぼっち』(イーストプレス)を発売。監督・脚本を務めた映画「i ai」が公開予定。
2009年、バンドGEZANを大阪にて結成。作詞作曲をおこないボーカルとして音楽活動開始。うたを軸にしたソロでの活動の他に、青葉市子とのNUUAMMとして複数のアルバムを制作。映画の劇伴やCM音楽も手がけ、また音楽以外の分野では国内外のアーティストを自身のレーベル十三月でリリースや、フリーフェスである「全感覚祭」を主催。中国の写真家Ren Hangのモデルをつとめたりと、独自のレイヤーで時代をまたぎ、カルチャーをつむいでいる。2019年、はじめての小説『銀河で一番静かな革命』(幻冬舎)を出版。GEZANのドキュメンタリー映画「Tribe Called Discord」がSPACE SHOWER FILM配給で全国上映。バンドとしてはFUJI ROCK FESTIVALのWHITE STAGEに出演。2020年、5th ALBUM「狂(KLUE)」をリリース、豊田利晃監督の劇映画「破壊の日」に出演。初のエッセイ集『ひかりぼっち』(イーストプレス)を発売。監督・脚本を務めた映画「i ai」が公開予定。







