海の中での潜水のごとく、ひとつのテーマについて皆が深く考え込み話し合う哲学対話。小学校、会社、お寺、路上、カフェ……様々な場で哲学対話のファシリテーターを務める著者は、自らも深く潜りつつ「もっと普遍的で、美しくて、圧倒的な何か」を追いかけてきた。当たり前のものだった世界が、当たり前でなくなる瞬間、哲学現在進行中。「え? どういう意味? もっかい言って。どういうこと、どういう意味?」……世界の訳のわからなさを、わからないまま伝える、前のめりの哲学エッセイ。
「親戚が好きになれない」。ある哲学対話で、参加者のひとりが言った。
家のさまざまなしがらみ、習慣、伝統などを受け継いでいかなければならないために、彼はしばしば親戚と集まらざるを得ないという。それでも、親戚が好きになれないと苦笑しながら話す。
墓を守るとはどういうことか、というテーマだった気がするが、あまり覚えていない。参加者はほとんどが初対面で、わたしにとっては見慣れぬ土地での哲学対話だった。それぞれの墓の守り方が紹介され、吟味され、議論される。どうすべきか、という建設的で解決に向かうような対話ではなく、むしろそれぞれが見ようとしていなかった自身の前提や欲求を丁寧に紐解いていくような時間だった。
2時間ほどの時間だったが、親戚が好きになれないと話した彼は、長い時間をかけて何度もそのことについて繰り返した。まるで親戚が嫌いな自分を罰するかのようだった。
対話も終盤に差し掛かったころ、ずっと黙っていた参加者のひとりである中学生の女の子が、不思議そうに男性の顔を見上げ、こう言った。
「別に嫌いなら嫌いでいいんじゃないですか」
この意見自体、そこまで斬新で、奇抜で、解決を与えてくれるような考えというわけではない。「親戚 嫌い」などとググれば出てきそうな意見でもある。
だが、彼女の意見は、主張というよりは「問い」だった。嫌いなら嫌いでいいのに、なぜそうしないのですか。なぜそう思うのですか。何があなたをせき止めるのですか。
問いを受け止めた彼は、しばらく絶句し「そうか」とだけ言った。彼は彼女の問いをひとりで反芻しているようだった。誰かが手を挙げ、またぬるぬると対話が再開される。わたしたちは対話の海を彷徨って、何かを探しにいく。だが、残念ながら時間がきて、対話は唐突に終わる。ハイみなさんそれでは陸に上がりましょう、とでもいうように、わたしはハイ終わりです、と味気なく対話を終わらせる。
皆が帰る準備をもくもくと始めるとき、絶句していた男性が「今日、本当に来てよかった」と言った。「そうか、嫌いでいいんですよね、あなたにそう言ってもらえてよかった、そうか」。少しうつむいて、緊張がほどけたように彼は笑い、どうもありがとう、と言った。お礼を言われた中学生は、やっぱり不思議そうな顔をして、黙ってそれを聞いた。
*
まったく別の日、まったく別の場所での、哲学対話でのこと。ある小学校の、何回目かの授業だった。彼らはもうすっかり哲学に慣れて、楽しみながら対話に参加することができる。その日は、彼らがやりたいと出してくれた「おとなとこどもの違いは?」にテーマが決まった。わたしの班は8人ほどのメンバーで、初回授業から説明や対話の途中で茶々を入れてくる男の子が入っていた。他の子が話している途中も、邪魔をしたり茶化したりしてなかなか場が集中しない。とはいえ、小学校ではよくある風景だから、なんとか仲裁しながら、哲学を子どもたちと楽しんだ。
だが、対話が始まってしばらくしたころ、彼は誰かが話しているのを遮って、体をぐねぐねと動かし、両手をせわしなくこすり合わせながら、目を細めてわたしにこう言った。
「本当は答え知ってるんでしょ」
答え、というのは、今回のテーマである「おとなとこどもの違いは?」に対する答えだろう。わたしの班では、年齢で決まるとか、お酒が飲めるとか、お金が稼げるとか、その違いをはかろうといろいろな意見が出ていた。彼は、あえてわたしの神経を逆なでしようと努めているような仕草で、大げさにうんうん、とうなずきながら続けてこう言った。
「いいんだよ、はやく言って。言っちゃいなよ、答え!」
彼はにやにやと笑っていた。わたしに手を差し伸べ、答えを促している。どうぞ、とでも言いたげな表情だ。
わたしはそれを見て、ほんとうに、泣きたくなったのだった。
毎回の哲学対話の説明で、わたしは何度も「答えをまだ誰も知らない、もしくはわかったふりをしているだけかもしれない」と強調していた。だからこそみんなで考えを出し合って、吟味するのだ、と言った。わたしも、先生も、おとうさんも、校長先生だって、この答えがわからない。だから「正解」を答えようとしなくていい、まずは考えを教えて欲しい、そう説明していた。子どもたちはそれをよく聞いていたし、彼がわたしに答えを求めたとき、他の子どもたちは「先生だってわからないつってんじゃん」などと介入してくれた。
だからその場ではもう一度、彼に向かって、彼一人だけに向かって、その説明を繰り返した。じゃなきゃわざわざみんなで考えないんだよ、わたしもわからなくて知りたいから、協力してほしい、と心の底からお願いした。彼はふん、と小さく息を吐いて何度かまばたきをした。別の誰かがはい!と手を挙げて、ぬるぬると対話が再開した。

対話が終わったあとも、彼の言葉がわたしの中で反響している。彼にあったのは、深い絶望だった。常に誰かの答えがあり、それを問われるだけという学校生活や彼の日常。後になって、彼が難しい環境にいることもほんの少しだけ知った。彼は最初の授業から、わたしたちを困らせる子どもで、そして困っている子どもだった。
考える授業っていったって、どうせ答えがあるのだろう。考える授業じゃなくて、答えさせる授業なんだろう。そういうもので、ずっとそうで、これからもそうだろう。
ああ、わたしもそういう子どもだった、と帰り道を歩きながら思い出す。そういうものだ、ずっとそうだった、これからもそうだろう。ぬるい倦怠感と、確かな絶望感だ。人生の主体がわたしではなく、何か大いなるものに奪い取られているような感覚。風は冷たく、帰り道は遠い。
横断歩道に立つと、向かいに見える寒そうなひとの群れが気怠げに口を動かしている。彼らの表情は見えない。黒いコートがずらりと並んでいる。
そういうものだ、ずっとそうだった、これからもそうだろう。
彼らは革靴を鳴らし、声を合わせながらどこかに歩いていく。
*
哲学対話は、日本だけでなく全世界で行われている。
学校などで行われる子どもとの哲学は、哲学対話という名前よりも「P4C(Philosophy for Children)」という名称のほうが一般的だ。ハワイ、オーストラリアなどの実践が有名だが、わたしはラテンアメリカでのP4Cが好きだ。ブラジルで活躍するウォルター・コーハンという哲学者は、P4C実践の動機として、ラテンアメリカの「貧しくて公正さを欠いた社会」で、ひとびとが「みじめさの感情」を感じられなくなっているということを挙げている。大人は公平さのない世界につぶやく。「そういうものだ(That’s the way it is)」「ずっとそうだった(It has always been like this)」と[i]。
だからこそ、コーハンは子どもたちにまなざしを向ける。受け身で無抵抗で、生暖かい倦怠感の中で絶望し切らないように。自分たちの生きている環境に対して「問う」ことができるように。彼はスラム街の小学校で、子どもと共に哲学する。「自分たちの生きている世界がほかでもありえたたくさんの可能性のなかの一つにすぎず、それゆえ自分たちの世界は自分たちで変革することも可能だと気づかせる[ii]」ために。
地道で静かでありながら、最もラディカルな彼の試みを、わたしは愛している。
「嫌いでもいいんじゃないですか?」と問われた男性のように、わたしも見知らぬ他者に、ふと問いかけられる。そういうもので、ずっとそうで、これからもそうだろう。わたしを取り巻いていたこの言葉が、あっけなく他者の手によって引き剥がされる。本当にそうですか?どうしてそう思うんですか?これからもそうなんですか?もしくは、他者の刺激によって問いを促される。これは問題なんだったっけ?そういうものなんだっけ?ずっとそうだったんだっけ?
本当にそれでいいんだっけ?
*
つい最近、ある授業で高校生たちと話していて、ひとりの学生が「そういうものだ、って言われるのがすっごく嫌」と言っていた。彼女は先生にどうしてこうなるんですか、などと問うと「そういうものだから」と言われるそうだ。「わからないならわからないって言えばいいのに」と憤慨する彼女は、パワフルで勇ましかった。他にどういうときに「そういうものだ」っと言われる?と問うと、彼女は記憶をさぐり、ああっと声をあげて「先生にわからないことを聞いたら「考えすぎるともっとわからなくなるよ」「そのうちつらくなるよ」って言われた!」と応えた。
ああ、それは本当に腹が立って、くやしくて、絶望しただろうな、と思う。学校というものに、先生というものに、失望しただろう。
そういうものだよ、考えすぎるとつらくなるよ、わからなくなるよ。
この思考停止を誘う言葉は、思いやりの形をとったアドバイスの容姿をしているからおぞましい。いつくしみ深い聖母の見た目をして、抱きしめられた途端にわたしたちの息の根を止めてしまう。気がついたら、あっという間に無抵抗で受け身の人間につくりかえられてしまう。
だが同時に「考えすぎるとつらくなるから、そういうものだと受け入れたほうがいい」という意見は、苦しみへのある種の防衛反応でもあることについても考える必要がある。哲学科に行きたい、と言った数年前、多くの人に「考えすぎるとつらくなるよ」「世界は存在するのか、とか問わなくていいでしょ、そういうもんだ、でいいじゃん」と説得されたのを覚えている。確かに哲学者といえば、一人で部屋にひきこもってぶつぶつ何かを口にし、どんどんおかしくなっていくイメージがまだまだ根強い。「自殺しないで」とお願いされたこともある。だが、わたしが実際に出会った哲学者たちはみな陽気で、よく喋り、冗談好きで、ちょっとした図々しさすらある。
なぜ考え問うことはつらくなると思われるのだろうか。確かに苦しいことも多い。いやな現実を前にして「そういうものだ」と捉えることで、自分を助けたこともある。だがそれは問いのせいというよりは、もっと別なところにあるような気もする。
皆が想像するような「問うひと」たち。彼らは顔をしかめ、頑固なシワを眉間に刻み、ひしゃげた身体をもてあまして、苦痛に苛まれている。考えることは苦しむことだ、とでも言いたげだ。だがもしかしたらその苦しみの原因は、考えることじゃなくて、孤立にあるのかもしれない。ひとりきりで思考の海に潜っているからかもしれない。たったひとりで、たったひとつの世界観、たったひとつの価値観、たったひとつの観点で、水中を彷徨っているからかもしれない。ひとりで水中を彷徨えば、いつかは行き詰まり、苦しくなる。そしてその苦しみを、問いの深淵さと取り違えるときもある。
だが哲学は、その構造において、他なるものを渇望している。
親戚を嫌いでもいいんじゃないですか?とか、それって何でなんですか、わたしは違う意見を持っています、というような、他なる声が、わたしの肺に新鮮な息を送り込む。わたしを閉じ込めているここは、大いなる海から見ればただの一部分にすぎない。世界はもっと多様で、奇妙で、無数の他なるものが存在する。その事実は、本当におそろしくて、そしてほっとする。
哲学は何も教えない。哲学は手を差し伸べない。ただ、異なる声を聞け、と言う。
ある夜、友だちからLINEが届いた。ひらいてメッセージを浮かび上がらせる。そこには「神が沈黙してるのはさ、うちらが他者の声を聞くためじゃね」とあった。文章のラフさと内容がアンバランスで笑ってしまう。同意の返事をしたが、なかなか返信がこない。あとから聞いたら、風呂に入っていたようだった。風呂の前にするLINEじゃないだろう。
あのときわたしは10歳の彼に、先生も校長先生もおとうさんも、誰も答えがわからない、と言った。彼は、はじめて目線を下に少し落としてしばらく黙り、最後の5分だけ、哲学対話に参加した。時間が来て授業が終わり、彼は遊びに教室を飛び出していった。
世界の究極の「答え」があるとしたら、神もそれを知らなかったらいいのにな、と少しだけ思った。
[i] Kohan, Walter O. “Philosophy and Childhood: Critical Perspectives and Affirmative Practices.”, Palgrave Macmillan, 2014.
[ii] 土屋陽介『僕らの世界を作りかえる哲学の授業』青春出版社、2019年。
*イラストも著者


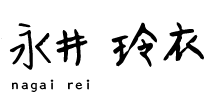 哲学の研究と、学校・まち・寺社・美術館などで哲学対話を開催中。好きなものは、詩と漫才と植物園。
哲学の研究と、学校・まち・寺社・美術館などで哲学対話を開催中。好きなものは、詩と漫才と植物園。