海の中での潜水のごとく、ひとつのテーマについて皆が深く考え込み話し合う哲学対話。小学校、会社、お寺、路上、カフェ……様々な場で哲学対話のファシリテーターを務める著者は、自らも深く潜りつつ「もっと普遍的で、美しくて、圧倒的な何か」を追いかけてきた。当たり前のものだった世界が、当たり前でなくなる瞬間、哲学現在進行中。「え? どういう意味? もっかい言って。どういうこと、どういう意味?」……世界の訳のわからなさを、わからないまま伝える、前のめりの哲学エッセイ。
夜のテレビは、クイズ番組ばかりだ。
難読漢字、地理、なぞなぞ、パズル、歴史、ランキング予想。とんぼの目はいくつある?トルコの首都は?□に入る文字は?マルかバツか?制限時間の中で、回答者たちは焦るように身を乗り出し、目を見開き、肩でぜいぜいと息をしている。
リレー形式の回答方法なのか、残り時間が数秒のところで、ある芸能人が最後の人に回答権をつなげている。だがその人は、問題を前にして答えることができないようだ。彼女は目が空洞になり、全身の力が抜けて、停止している。彼女は何も答えない。失敗を知らせる大きな音がして、彼女を取り囲む他の出演者が、頭を抱えて悔しがる。わたしはテレビを消して、失敗のブザーを頭に響かせたまま、眠りにつく。
目を覚まし、目にする朝の芸能ニュースでは、アイドルが自分のエピソードを披露している。かと思えば「さて問題です。このあとどうなったでしょう?」と、画面の中から突然問いかけられる。
だらしなく口を開けたまま、寝起きの頭でうっすらと考えてみる。誰もいない部屋の朝は湖のほとりのように静かで、さみしくて、よそよそしい。スタジオに座るひとたちが、張り付いた笑顔で短く刻まれる時計の音とともに、予想を交わしあっている。「正解はCMのあと!」と出題者のアイドルは冷え冷えとした微笑みを見せて、ポーズをとる。すべてが過剰で、何かが欠如している朝だ。
ゆっくりと血を送るように考えてみる。だが、言葉と言葉が散らかって結びついていかない。アイドルが誰だったのかもうまく思い出せなくなる。マルちゃん正麺、匂いのつかないムシューダ、過払い金。このあとどうなったでしょう。このあと。あのひとが、どうなったか。なる、というのは何か。キリンビール、伊藤ハム、ソニー損保。なる、する、ある、いる。
気がついたら番組は終わっていて、結局答えが何だったのかを見逃してしまう。その代わりに、昨晩クイズ番組で答えられなくなったあの時の彼女の表情が浮かんでくる。問いを前にして全身の力が抜けるあの感覚も。この問題はわかりますか?あなたのビジョンは?あなたはどうして生まれてきたのですか?
中学の時の期末試験が本当に、何も、わからなかったことが思い出される。頭の中が言葉や数字でぐちゃぐちゃになって、自分が誰で、ここがどこなのかもわからない。自分が何を問われているのかもわからない。自分の字が、自分の字ではないみたいだ。身体の内部に、胸からじっとりと冷たい水がつたっていく感覚がする。水はどろりと腹部に落ちて、全身にゆっくりゆっくり広がっていく。力が抜けていき、不思議とひどく眠くなってくる。問いはわたしの前で分散し、すべてはあいまいになっていく。
そう、あれは、あきらめの感覚だ。
*
とある学校の中学1年生と哲学対話をした。テーマは「人間」で、とりわけ「本能」について生徒たちは話したがっていたようだった。コロナの影響で直接顔を合わせる機会がなかったせいもあるのか、少しだけぎこちなく対話がはじまる。頭の切れそうな子が、ハキハキと植物やウイルスの類比をつかって、子孫をのこすことについて語っている。「人間の本能は増えたい、ということではないでしょうか」。他の子がそれに反応し、だんだんとにぎやかに、対話が進んでいく。
だが対話は、少しずつ不穏な雰囲気に満ちてくる。誰かが「人間って、子孫を残すために生まれてきたのかな」と言う。わたしが生きているのも、子孫を残すため?
とたんに子どもたちがわあっと声をあげる。いやだ、こわいこわい、いやだ!予想以上の反応の大きさに少しおどろく。大人たちの哲学カフェでは「子孫を残す」というワードは、「まあそんなもんでしょう」という心得顔と共に出されることが多いからだ。喧騒の中で、ひとりの少年が不安そうにぽつりとつぶやく。
「ぼくたちは、いつも子孫繁栄しないといけないのかな」
ああ、と声がもれてしまう。13歳の少年は、目の前で心細そうに座っている。
生まれたときから少子化で、不景気で、税金が足りなくて。小学生のころ「日本の未来のために、たくさん子どもを産んでね」と言われたことが頭をよぎる。産めよ、増えよ、地に満ちよ。女性には地元に帰って、たくさん子どもを産んでもらわなければいけません。つくりましょう、生産しましょう。あなたたちは産めよ、増えよ、地に群がり、地に増えよ!
「社会って、共同体って、どうしても続けなきゃいけないんでしたっけ」。誰かが、どこかで言った言葉がよみがえる。いつだったかも、誰の言葉かもおぼえていない。ただ、生々しい声だけが耳に張り付いている。産めよ、増えよ、地に満ちよ。つくりなさい、つづけなさい、永遠に。
生徒たちはこわい、こわいとまだ騒いでいる。どうしてこわいの、問いかけて、考えようとする。感情だけがゴールではない。その後ろにも必ずそれぞれの理由がある。ひとりが手を挙げて、言葉を探しながら話し出す。
「人間の生きる目的が繁殖することなら、すべてが、いまここで話したり、考えたりすること、それもぜんぶ、ぜんぶ無駄になる」
無駄だ、ぜんぶ無駄だ!お調子者の少年が、それを聞いて声を張り上げる。彼は苦笑いをして、手を大きく振ってわたしに提案する。「先生!考えるとむなしくなるから、これはもうやめよう!」
生徒たちはお調子者の言い方にどっと笑って、彼を見ている。彼は「真実を知るとむなしいから」と悟ったようにほほえみ、椅子にどっかりとよりかかる。何人かは集中力が切れて、別のおしゃべりを始めている。だが「ちがう!」と誰かが叫んでいる。あれ、これはわたしの声じゃないか、となぜだか遅れて気がつく。
待って、絶望するな、ちがう、ちがう、考えよう、まだわからない、まだわからないよ!わたしは気がつくと、喧騒の中で声を枯らして叫んでいる。こわい、そんなのいやだ、そう思うことはなぜで、そう思うならどこかが違うはずで、そうじゃない仕方はあるのか、そうだとしても、それが何なのか、考えたいよ。なにかに突き動かされるように、声を張り上げる。
そもそも本能と、人間の価値はまた別の話なはずで、まだたくさん、たくさん考えることはある。まだわからなくて、真実なんてすぐに出るわけがなくて、どうなるかわからないのに。
むなしさと、あきらめに屈してしまいそうな問い。わたしたちは、繁殖するためだけに生まれてきたの?わたしたちの価値は、生産性ではかられてしまうの?わたしは生きてていいんでしょうか、わたしはこれでいいんでしょうか。子孫を残さないといけないんですか。人間の本能が子孫を残すことなら、人間の価値は子孫を残すことで決まりますか。
人間に崇高な価値があって、使命があって生まれてきたんだと思いたいわけではない。生きていることそれ自体が価値であるという言説も溢れかえっていて、よくわかって、そのとおりだと思う。そしてある種の「答え」もいっぱいある。生物学的な答えだってあるだろうし、社会学的な答えもあるだろう。でも結局、わたしが考えるしかなくて、わたしが引き裂かれるしかない問いである。
わたしたちには、問いがある。時にばかばかしく、時に頭を抱え、ぼろぼろ涙が出てしまいそうになる問いが。
いつまで働き続けなければいけないんでしょうか。
ひとを愛するって、どういうことなんですか。
ふつうって、何ですか。
わたしは、生まれてきてよかったですか。
*
日々はわたしに、探求することの快感と苦痛を教えた。わからないことは増えていき、むしろわかっていたと思っていたことが、フィルムが剥がれるように、ほころびを見せて、見知らぬものとして迫ってくる。わたしたちは、転びながらも、答えを見つけようと走りつづける。
そしていつか、走り疲れるときがくる。硬い地面に膝をつき、どこからも力が湧いてこないのを感じる。指一本も動かすことができない気がして、地面に横たわってしまう。そして、ゆっくりと、あきらめが近づいてくる。あきらめは外からやってこない。内側の奥底から、じわり、じわりとやってくる。胃の腑が冷え切って、とろりとした眠気と、世界にもやがかかるのを感じる。
だが、問いはわたしの影のように、そばにいる。そのときに気がつく。問いは、時にわたしを苦しめ、時にわたしをはげます存在であることに。
あきらめがわたしを喰い破りそうになるとき、問いがわたしを心配そうにのぞきこむ。わからないと投げ出したくなったり、早急に答えを決め込みたくなったりしたとき、まだわからない、まだわからないよ、と問いは言う。
そして問いは、年も所属も時代も超えて、見知らぬわたしたちをつなぎとめてもくれる。労働に疲れ、ぐったりと身体を電車の座席にあずけているとき、ふと13歳の少年の問いが目の前に立っていることに気がつく。彼とはたった一度しか会わなくても、こうして同じ月を見るように、同じ問いを考えることができる。
だから、たとえ問いに打ちひしがれても、それでも問いと共に生きつづけることを、わたしは哲学と呼びたい。哲学は、慣れ親しんでいる世界を粉砕し、驚きをあたえ、生を不安にさせて役目を終えるのではない。息切れをして、地上に倒れてもいい。心細くなって、頭を抱えてもいい。それでも、人々と、問いと共に生きることをやめないことだ。
今日の夜も、テレビからはクイズ番組が流れている。制限時間がせまっているのに、回答席からなかなかどかずに、しがみついてもがいているひとがいる。周りから、パスしな!パス!と声がかかる。だが彼はその問いを頭にめぐらせて、あきらめずに、考えている。
いつまでも、いつまでも、彼は考えている。


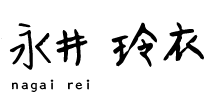 哲学の研究と、学校・まち・寺社・美術館などで哲学対話を開催中。好きなものは、詩と漫才と植物園。
哲学の研究と、学校・まち・寺社・美術館などで哲学対話を開催中。好きなものは、詩と漫才と植物園。