海の中での潜水のごとく、ひとつのテーマについて皆が深く考え込み話し合う哲学対話。小学校、会社、お寺、路上、カフェ……様々な場で哲学対話のファシリテーターを務める著者は、自らも深く潜りつつ「もっと普遍的で、美しくて、圧倒的な何か」を追いかけてきた。当たり前のものだった世界が、当たり前でなくなる瞬間、哲学現在進行中。「え? どういう意味? もっかい言って。どういうこと、どういう意味?」……世界の訳のわからなさを、わからないまま伝える、前のめりの哲学エッセイ。
「途方もない質量がこわい」と言うひとがいた。友だちにサイコロ状のものを手渡され「これには宇宙と同じ質量が詰まっている」と言われた夢がトラウマだという。その場にいたひとたちはみんな笑った。だが彼は、あまりのこわさに号泣しながら目覚めたらしい。
親指と人差し指でつまんで持つことができてしまうほどの小さなサイコロ。その中には、途方もないエネルギーと物質がぱつんぱつんに詰まっている。それがなぜ存在しているのかは分からない。なぜ友人が持っているのかもわからない。そして、なぜ自分が手渡されようとしているのかも。不可解なことばかりだ。
でもどうしてそれがこわいんですか、と聞いてみる。彼は「わからない、どうしてだろう」と黙ってしまった。
その話を聞いていて、わたしにも、理由はわからないがこわいものがあることを思い出した。それは「ひとがあっけなく死ぬ映画」である。わたしにとって最もこわいのは、ひとびとの恐怖を駆り立てるホラー映画などではなく、戦争映画やスパイ映画、ヒーローものなどのアクション映画で、「場の流れ的に」ひとが死ぬシーンだ。親友や愛する人の死は重い。クライマックスで、劇的に描かれ、壮大な音楽がかかる。だが、最初に撃たれる登場人物Aは、主人公の巧みな銃さばきを紹介するためだけのシーンであっけなく命を落とし、二度と思い出されない。
登場人物Aは、名前がない。つけられていないからだ。性格も存在しない。設定されていないからだ。有名俳優でもない。誰でもできるからだ。だが、このひとには、生活が存在した。わたしたちが知り得ない、だがわたしたちと同じような生活の営みが。
M-1グランプリの霜降り明星の漫才を見ておどろいた。決勝戦のネタで、ボケのせいやがプールで溺れ「頭の中に走馬燈がかけめぐる」と白目を剥く。「死にかけとるがな」とツッコミの粗品。ボケのせいやが走馬燈として、そのひとの様々な思い出や人生を再現しはじめる。「マメでかー!」「関節鳴らへんなあ」「この道に出てくんねんな」。それを見たツッコミの粗品が「しょうもない人生!」と叫ぶ。
どきりとした。だってこの人生は、まぎれもなくわたしたちの人生だったから。
お笑い芸人や、詩人、作家は、個人的で、普段は目に見えていない生活の営みの中の体験を言語化するのが本当に上手だ。わたしたちは信じられないほどばらばらなのに、なぜだか共有できている知覚や、記憶、体験がある。そんなものを彼らにふと掘り当てられたとき、哲学的な真理にたどり着いたような心持ちさえする。
便座は恐らく冷たいだろう / 又吉直樹
お笑い芸人でもあり、作家でもある又吉直樹の自由律俳句。ここには大きなエピソードや、心震える美はない。だが、誰もが覚えのあるような日常の断片がある。ここまで言語化されなくとも、ひんやりとした白の便座から、冷たさのイメージを受け取ったことがあるひとは多いのではないだろうか。
わたしたちは大いなる物語を求める。劇的で、印象的な出来事を、大切に覚えている。自分を語るときは、それぞれの人生ハイライトアルバムがあり、それを思い出しながら自分を紡いでいく。ハイライトアルバムがうまく作れていなかったり、思い出せなかったりするひとを「うすっぺらい人間」なんて呼んで揶揄することもある。
だが、わたしたちはこのような非常に具体的で忘れてしまうような、本当にちいさなちいさな出来事や感情や知覚でもできている。意識にのぼらない、しかし時にひとびとと共有しうる体験、そして忘れて、どうでもいいとされて、取るに足らないとされているもの。その無数のまたたきの粒で何とかわたしという輪郭を保っている。
フランツ・カフカは「なぜ人間は血の詰まったただの袋ではないのだろうか」と書いた。ただの袋だったらどんなに気が楽だろう。そうではなく、人間は宇宙の質量が詰まったサイコロなのである。宇宙の中に数え切れず把握しきれないほどの星があるように、小さな小さなつぶつぶがあわさってできている。こんな小さな身体に、つぶつぶがぎゅうぎゅうに詰まって、恐ろしい質量を持っている。
手渡されるサイコロは、わたしたちのことなのだ。
それを「いのち」と呼ぶひともいるだろう。いのちに詰まっている、無数の歴史、知覚の連なり、思考の広がり。アクションシーンで登場人物Aが死ぬシーンは、宇宙の質量が詰まったサイコロが、ただの血の詰まった袋であるかのように扱われるから、こわいのかもしれない。
*
よく哲学は、大きくて、ドラマチックで、抽象的な概念だけを取り扱うと思われている。生とか精神とか形相とか。すべてにビックリマークがつきそう。哲学の学会に行くと、ばんばんそんな言葉が飛び交って、花火を見ているような心持ちになる。もちろんこれはこれで意義があるし、面白いことも多い。でもそればかりだと、どこに自分がいたらいいのかわからなくて、ふと心細くなる。学生時代のバイトで嫌なことがあった帰り道、とおくとおくとおくの知らないまちで花火が上がっているのが、ビルの隙間からほんの少しだけ目に入った時のことを思い出す。すごくきれいで、圧倒的で、華やか。でもその花火は、わたしのものではない。わたしの手からすり抜けて、どこか知らないひとのために打ち上がっている。わたしは疲れた身体をひきずって、だれもいない暗い道をうつむき歩きながら、とおい花火の音を聞いている。
あるまちでの哲学対話にファシリテーションとして呼ばれたときのこと。大学の偉い先生をゲストにした上で、哲学対話をするという会があった。当時のわたしは、ファシリテーションもそんなに慣れておらず、本来対等にひとびとと議論する場である哲学対話に、偉い先生が偉いままに混じっているという難しい状況に対応しきれないでいた。とはいえ対話をするはずなのだからと、専門用語を使わないで、ひとびとと共有できる自分の言葉で話すルールなどを最初に話し、哲学対話をスタートさせた。問いだしから始めようと、口をひらきかけると、先生がわたしをさえぎり「世界の世界性が」と言った。
大きく鮮やかな花火が打ち上がる。わたしはこれを、ひとびととしあわせな気持ちで眺めたり、自分だったらどのように打ち上げようか考えたりするときも、もちろんある。だが、その日参加しているひとは、先生のファンだと思われる男性以外のほとんどが、そのまちに昔から住むおばあさんや、おしゃべりが好きで来てくれた女性たちで、彼の言葉も、感覚も、そして問いすらも分かちあってはいない。どこかとおいところで、見えない花火が打ち上がっている。いや、まずはみんなで何について考えようか考えようと、その先生を見やるが、花火は止まらない。ラカン、ハイデガー、ヴィトゲンシュタイン。地平、世界、様相、現象。えらいひとの名や、大きく抽象的な概念、専門用語もどんどん乱発される。対話はブレーキがきかないまま、どんどん前に進んでしまう。先生のファンだという男性が、後を追うように花火を盛大に打ち上げる。特定のひとにしか見えない花火を。
とうとう最後まで、そのまちに住んでいるひとたちが話す機会は与えられなかった。何度か介入し、ルールを確認して、ひとびとと共有できるテーマを設定しようとしても、火薬の匂いにむせかえりそうになるほど、先生たちは花火を打ち上げ続けた。そしてわたしにも、最後までその花火は見えることはなかった。
会が終わり、先生たちの懇親会に向かう途中の道でひとり呆然としていると、参加者のおばあさんが近づいてきた。そのひととは、以前何回か哲学対話をしたが、直接話したことはなかった。彼女はぼうっとしているわたしの手をとって、自分の孫のように自分の手とつないで、坂の途中に木が植わっている場所にわたしを連れて行った。風があつい頬にあたる。ベビーカーを押した女のひととすれ違う。ごとごとと音をたてて、車がゆっくりと通り過ぎる。歩道をとおり、その脇にひっそりと佇む切り株が目に入る。おばあさんは立ち止まり、うつむいたまま話し出す。
ここには、わたしのすきな木があったのよ。いつもお家の前を掃除するとね、この大きな木が目に入って、あいさつをして。昔からある木でね。でも、あるとき、しらないひとたちがきて、許可もなくこの木を切っちゃったの。かなしかった。ほら、切り株になっちゃっているでしょ。
わたしにもお気に入りの木や草がある。何かの拍子にそれがなくなることもある。切られちゃったな、かなしいな、と歩きながら思う。ささやかな、手のひらサイズの、日常の断片だ。ただ一般的な人生のハイライトアルバムにはたぶん載らない。わたしのあまりにささやかな日常の揺れ動きだから。でも、わたしはそのかなしみを知っている。
高いところにいるひとたちの話はぜんぜんわからないけど、この木のお話は、あなたに聞いてほしかった。くだらないこと言ってごめんね。
おばあさんはそう言って両手でわたしの手を握った。いえ、さっきの対話にあったどんな発言よりも価値のあることです、とわたしは涙をこらえて言った。生まれてはじめてひとにやさしくされた気がした。
*
すきな木が切られて、かなしかった。ここからでも、哲学ははじめることができる。だから、哲学対話はそんな日常の断片が飛び交う。「哲学」なんてかっこいい名前なのに、「小学校のときの給食の味噌汁に入っているちょっと煮込まれすぎてどろっとなったわかめ」なんてものが主題になったりもする。普段の意識にのぼらず、どうでもいいとされて、議論のテーマにもならず、取るに足らないとされているもの。そんなことについても、考えることがゆるされる。あの時は、細かな断片だけど、なぜか共有できているどろどろのわかめを思い出してみんな笑った。そう、そのときの哲学対話は「不気味」というテーマだったのだ。世間はハロウインで、これももうずっと前のことだ。
哲学はすべてのひとに関係する。すべてのことに関わることができる。重要でないと思われているものも、哲学対話では考えることができる。むしろ、普段は忘れられているようなものや、問われもしないようなことに耳を澄ませる。そしてまた同時に、議論の場で取るに足らないとされ、話を聞かなくてもいいとみなされているひとの話にも耳を澄ませる。人間を、ただの血の詰まった袋ではなく、宇宙の質量を持つサイコロとして扱う。ともに知を愛するために、本当の意味でともに哲学をするために。
夢を見た彼はサイコロを渡されるのがこわいと言った。今なら少し分かるような気がする。哲学対話では、誰かが考えを話すとき、まるでそのひとが、自分自身の一部をわたしに手渡してきたかのように思えるときがある。その考えは、そのひとなのである。
だからこそわたしたちは恐れるだろう。手渡されたサイコロを手から滑らせて落としてしまうことを。映画であっけなく殺されるような仕方で、誰かの考えを扱うことを。誰かが手渡してきたその考えは、ただの音ではない。それは声として聞かれる。宇宙の質量をもったいのちとして聞き取られる。
「いのちはかけがえがなく愛おしい」と言いたいわけではない。むしろ満員電車などでひとびとと身を寄せ合うとき、誰のことも愛しくないと思う。だが、誰のことも排除したくないと思う。傷つけたくない。あなたを壊してしまうこと、あなたを損ねてしまうことがこわい。でもやっぱりそれはなぜだかわからない。


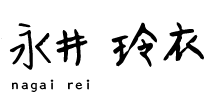 哲学の研究と、学校・まち・寺社・美術館などで哲学対話を開催中。好きなものは、詩と漫才と植物園。
哲学の研究と、学校・まち・寺社・美術館などで哲学対話を開催中。好きなものは、詩と漫才と植物園。