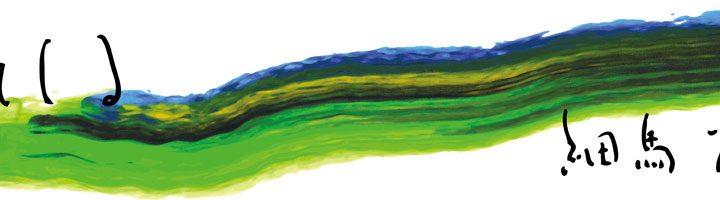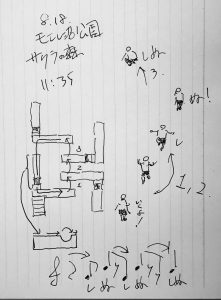駅前で昼食の弁当を食べようと木陰をさがしていたら、ちょうどクスの木の下に頃合いのベンチが空いていた。いそいそと包みを開きかけたところで男の声がした。
「×××××!」
顔を上げて見回すと、少し離れたところに座っていた老夫婦がこちらを見ている。男性の方が、わたしの足もとを指して再び同じことを叫んだ。それが、なんということばかが分かったのは、彼が少しゆっくり言い直してからだった。「そこ、ありいっぱいですよ」。それで、彼が何を言っていたのかわかった。彼は「ありだらけ!」と言ったのだ。あわてて地面を探したが、それらしきものはいない。「いや、もうちょっと横」。少し視線をずらしたら、いたいた。誰かがアイスクリームでも落としたのだろうか。白いしみのようなものが地面にへばりついており、そこにアリがわらわらたかっている。「そいつら、弁当までのぼってきますよ」。わたしはあわてて弁当を包み直した。女性も「ありだらけやったな」と言い、「なあ」とご夫婦はもう一度顔を見合わせている。ほんまにありだらけですね、ありがとうございます、と礼を言ってから、少し離れたところに座り直した。ようやく人心地して弁当を口にしてから、さっき男性からかけられたことばが妙におかしくなってきた。
「あ、あり」でも、「あ、そこ」でもなく、いきなり「ありだらけ!」。わたしがとっさに何のことか分かりかねたのは、彼があまりにこなれた口調ですらすらと、「ありだらけ!」と言ったからで、それは「アリ」といういきものを指しているというよりは、早口で唱えられた呪文か何かのようにきこえたのだった。
***
あの男性は、わたしの足もとにアリを見つけた瞬間に「ありだらけ!」ということばをいきなり思いついたのではなかったのではないか。おそらく、わたしが弁当を開こうとしたのとまさに同じ位置に、あのお二人は座りかけたのだ。そしてどちらかがアリに気づいた。気づいた最初のことばはたぶん「あ!」とか「ひゃあ!」とか言うものだっただろうし、続くことばもたぶん「あり!」「うわあ!」というものではなかったか。アイスクリームの滴か何かにたかっているその様子を「ありだらけ!」と的確に述べることができたのは、そうしたいくつかの驚きのことばを経たあとである。女性が言ったのか男性が言ったのか、とにかく、その「ありだらけ」ということばは、この驚くべき体験をぎゅっと圧縮したことばとして響き、二人の脳裏にしっかりと焼き付いたに違いない。わたしは単に「ありだらけ!」という注意を受け取ったのではない。たった五つの音に濃縮された二人の経験を受け取ったのであり、だからそれはにわかには分からない、謎のことばのつぶてとして響いたのだろう。よくよく考えてみれば、わたしがいま使っていることばのひとつひとつもまた、ずっと遡っていけば、誰かの経験を濃縮したものだったのではないか。
***
昔、吉本隆明の『言語にとって美とはなにか』を読んだとき、そこに書いてある原初の言語の発生のくだりに、感銘と同時に違和感を持ったことがあった。
「たとえば狩猟人が、ある日はじめて海岸に迷いでて、ひろびろと蒼い海をみたとする。人間の意識が現実的反射の段階にあったとしたら、海が視覚に反映したときある叫びを〈う〉なら〈う〉と発するはずだ。また、さわりの段階にあるとすれば、海が視覚に映ったときの意識はあるさわりをおぼえ〈う〉なら〈う〉という有節音を発するだろう。このとき〈う〉という有節音は海を器官が視覚的に反映したことにたいする反映的な指示音声だが、この指示音声のなかに意識のさわりがこめられることになる。また狩猟人が自己表出のできる意識を獲取しているとすれば〈海(う)〉という有節音は自己表出として発せられて、眼前の海を直接的にではなく象徴的(記号的)に指示することになる。このとき、〈海(う)〉という有節音は言語としての条件を完全にそなえることになる。」(吉本隆明『定本 言語にとって美とはなにか Ⅰ』角川ソフィア文庫)
突っ込みどころはある。日本語では海はいかにも叫びらしい〈う〉から来たようにきこえるが、英語でsea、フランス語でla mer、はたまたマレー語でlautというときの来歴はどうなるのか。それに、〈う〉と叫びたくなるような驚きの対象は、世界にいくつもある。眼前に広大な平原が現れたときの〈う〉は、山が現れたときの〈う〉はどうなるのか。海を見たときの叫びだけが特別に〈う〉として定着する理由はどこにあるのか。
にもかかわらず、わたしが感銘を受けたのは、この論が、言語の発生に「反射」と「(意識の)さわり」という二つの段階を見いだしていたからだ。個々の経験に対してその都度発せられる叫びは「反射」だが、その叫びとともにかつての経験とのつながりがうっすらと意識されるとき、それは「さわり」となる。この吉本隆明の一節では、象徴や記号が、ある経験から別の経験を同時に立ち上げる声として論じられている。そこにぐっときたのだった。
一方で、わたしが違和感を感じたのは、吉本隆明の描く浜辺には、一人の狩猟人以外他の誰もいない、ということだった。たとえある一人の狩猟人のなかで、さまざまな海という体験が〈う〉という声のもとに結ばれたとしても、それが一人合点である限り、言語にはならない。言語は誰かから誰かに発せられるものであり、その〈う〉という声が、わたしではない別の誰かの経験、別の誰かの海を立ち上げない限り、言語としては成立しないはずなのである。
誰かの言った〈う〉が、ただの叫びではないことに気づくためには、それが叫んだ当人の経験とわたしの経験をつなぐものであると、わたしが気づく必要がある。わたしはその声に、「(意識の)さわり」を聞き取る。叫んだ当人に「さわり」が立ち上がるだけでなく、わたしにもそれが「さわり」として立ち上がる。そして、ついにはわたしも〈う〉を口にする。そこまで来てようやく、〈う〉は原初的なことばとして成立する。
この問題をとくには、わたしと誰かがある日あるとき同じものに注意を向けていること、同じことに囚われながら声を発する事態を考える必要がある。実際、近年の乳幼児の言語発達研究では、単に乳幼児だけでなく、養育者と乳幼児とモノとの三項関係を微細に検討することが、重要視されている。
わたしのいま使っていることばをどんどん遡っていくと、そこにはどんな原初的なことばが広がっているのだろうか。そこには少なくとも、狩猟人は二人以上いるだろう。一人の〈う〉が他の誰かの〈う〉を立ち上げ、海が立ち上がる。そのときはじめて〈う〉は海の〈う〉になるだろう。
***
弁当を食べながら、ふと、アリからも老夫婦からも離れすぎた場所を選び直したことを少し悔やんでいた。老夫婦とももっと話せばよかった。それにここでは、他の誰かがアリに近づいたときに、声をかけることができない。なんとなくもう一度「ありだらけ」と口にしてみたかった。
Profile
 1960年生まれ。滋賀県立大学人間文化学部教授。専門は人どうしの声の身体動作の調整の研究。日常会話、介護場面など協働のさまざまな場面で、発語とジェスチャーの微細な構造を分析している。最近ではマンガ、アニメーション、演劇へと分析の対象は広がっている。『介護するからだ』(医学書院)、『うたのしくみ』(ぴあ)、『今日の「あまちゃん」から』(河出書房新社)、『ミッキーはなぜ口笛を吹くのか』(新潮選書)、『浅草十二階(増補新版)』『絵はがきの時代』(青土社)など著書多数。ネット連載に「チェルフィッチュ再入門」、マンバ通信の「おしゃべり風船 吹き出しで考えるマンガ論」などがある。
1960年生まれ。滋賀県立大学人間文化学部教授。専門は人どうしの声の身体動作の調整の研究。日常会話、介護場面など協働のさまざまな場面で、発語とジェスチャーの微細な構造を分析している。最近ではマンガ、アニメーション、演劇へと分析の対象は広がっている。『介護するからだ』(医学書院)、『うたのしくみ』(ぴあ)、『今日の「あまちゃん」から』(河出書房新社)、『ミッキーはなぜ口笛を吹くのか』(新潮選書)、『浅草十二階(増補新版)』『絵はがきの時代』(青土社)など著書多数。ネット連載に「チェルフィッチュ再入門」、マンバ通信の「おしゃべり風船 吹き出しで考えるマンガ論」などがある。