2021年、最初の蝉が木にしがみつき鳴いたのを聞いた。NO FUTUREな展開を突きつけてくる混乱の日々の中でも当たり前に季節は巡り、またこの季節がやってきた。結局何かに期待している。窓を開けて、風を招き入れ、蝉の唸る声を聞き思い出す。去年の8月のこと。
会って10分くらいだっただろうか。佐内正史は「詩を読んでいいかな?」そう言ってiPhoneを取り出し初対面のわたしの部屋で自作の詩を音読しはじめた。詩を読む途中で佐内さんの目線が部屋の角に立てかけられたギターに目が行き、その視線がこう誘う。「Join me!」
8月の寝ぼけた頭のわたしの全身に血が巡り出すのを感じ、乾いた木に張られた六弦を弾いて音読に重ねた。内容は入ってこなかった。けど、何を放っていたかじゃない。そのでたらめなほど軽快なステップの埋まり方が詩そのものだった。音読が終わると唯一の聴衆だったエッセイの担当編集者から乾いた拍手を数秒もらった。不思議な空気が部屋の中でゆっくり回り、蝉の咽び泣く声が窓の奥で聞こえていた。
「どこで撮影しよう? とりあえず表走る?」そう言って8月の終わり、焼けたコンクリートの上を一緒に走る。解けた靴紐を結ぶためにしゃがみ込むと額から汗の玉が落ちる。蟻の大群が頭のないバッタを運んでいた。みんなそれぞれのやるべきことをやっている。「きばれよー」
蜃気楼の先で佐内さんがカメラを手に持ち立っている。わたしは立ち上がり、今度は自転車で走り出す。青い風が髪を後方に運び、そしてばらける。

昼はカレーを食べに行った。給食の延長みたいな「少年ジャンプ」のようなカレーにやや強すぎる冷房の風、汗が乾いていく。おばあちゃんがやっている店だからか、テレビのボリュームは大きすぎる。佐内さんのスプーンを持つ手は重そう。うんと眠そうだ。わたしは内心、走ったからじゃん!と思っていたが言いはしなかった。午後からも撮影の続きをする。わたしの出版する『ひかりぼっち』というエッセイのための撮影だった。そんな風に初対面の日は夏の風景として胸に焼きついた。
「マヒトくん、ふわふわ食べにいく?」
そう電話が朝にかかってきて二人でパンケーキを食べに行ったり、カレーを食べに行ったり、それからはそんな感じで日々の隙間を縫って遊んでいて、その流れで映画「i ai」のビジュアルの撮影をお願いしたのは自然なことだったように思う。
そうこうして2020年を越す。このコロナを取り巻く世界は、根拠はないけど少しずつよくなる。そんな年を越して晴れた気分を大切にしたい。そんなツイートをした正月から4日後、バンドのベースであるカルロスが脱退する。正月に明石に帰って、きっと家族や友人に会う中で決心が固まったのだろう。暗闇が吹き出し、通い慣れたいつもの駅からの帰り道で迷子になる。しゃがみ込んだコンビニの前でわたしは静かにツイートを消した。
カルロスはラッキーボーイだった。「それめっちゃええやん」。根拠や理由などなくそう言い切る。歯切れの良さに自分は選択を迫られた時、救われていたのだと思う。その不在を初めて痛感したのは映画ビジュアルの撮影の時だった。3人になったGEZANとしては最初の勝負の日だった。本当は夕暮れの中で撮影したかったが、分厚い雲がかかり灰色が空を覆った。冷静に考えればそんなわけないのに、不安定な自分は天候を逃したのは勝負の神様に見放されているからだと勘ぐり、空を睨みつける。
カルロスは「いや、むしろこの灰色の雲が逆にええな」と真顔で言えるやつだった。わたしはその時、いつも脇にいた人間の不在を知った。
ギターのイーグルはそれを察知すると同調し一緒に暗くなる。こいつはこいつで優しいやつなのだ。だが、優しすぎて勝負ごとには向かない。
そんな中、待ち合わせの時間に遅刻してきた佐内さんが黄色のスカイラインに乗って登場する。稲妻のようだった。空気が一変する。
防火服に火をつけ、炎があがる中でギターをかき鳴らす姿をフィルムでSHOOTする。まさに時間を撃っていた。

後日、その出来上がりの写真を見ながら、この勝負には勝ったと思った。存在することの必然はいつだって試されている。わたしはいつも自分の現在地を、内なる自分にはとやかく聞かずに周りにいる美しい景色や人で測っている。わたしが勝負の神様に愛されているかどうか、生まれてきたものの純度でもって測っている。
ファウストは見捨ててなどいない。この螺旋の中で回転数をあげるようわたしを駆り立てていた。
翌日、佐内さんから電話で「ムービーも回そうかな」と名乗り出てくれた。断る理由などなかった。紛れもないラッキーボーイだ。
それからはもう映画研究会の部室のように部屋で映画を見ながらああだこうだしている。「STAND BY ME」見たりね。
タバコに火をつける。コーヒーが汗をかく。網戸から風が入ってきて、日焼けし始めた腕の細い毛を撫でる。大きな展望、なんでもない時間。お菓子の空袋が机の上に広がっていく。i aiの夏というやつが始まった。

うだるように暑い夏が始まる。最近上手く眠ることができない。寝不足で歩く街、コンクリート。マスクをしているせいか直射日光に立ちくらんだ。相も変わらずニュースはクソをタレ流していて、全体的に最悪。バカみたいなこと言うけど最高な仲間を作って最高の時間でもって復讐するしかない。この夏はどんな出会いが待ってるのかな?
毎週、ミーティングをして、ずっと脚本を書いている。書き込みすぎて、「分量を三分の一にしないとこの予算じゃ収まらないよ」とプロデューサーに言われる。マジか〜。
なんで映画を作るのかなんてたまに聞かれるけど、なんで今回の設定が人間だったのか答えられないように、理由なんてわからないよ。
じゃあわからないのに、なんでこんな風に駆けたくなるのだろう? このカルマ、困るなー。
でも。きっとこの蜃気楼の先に探していた永遠というやつがあるはずだ。嗅覚がそれを確信して、体を休ませてくれない。
この焦燥も混乱も迷いもサヨナラもきっと残ってしまう。それを愛しいと呼び切るために。
できるだけ恥ずかしくいたい。本当だから。
photography 佐内正史/山本光恵
Back Number
- 第21回 WISH 2023-12-24
- 第20回 Million Wish 2023-07-26
- 第19回 インドの灼熱、立体の祈り 2023-06-09
- 第18回 阿寒ユーカラ ウタサ祭り 2023-02-09
- 第17回 作ることの喜び、背負うことの怖さ 2022-11-15
- 第16回 真夏のピークが去った 2022-09-01
- 第15回 三月のこと 2022-03-31
- 第14回 フジロック2021 2021-08-18
- 第13回 i aiの夏 2021-07-19
- 第12回 十三月農園と種苗法 2020-10-05
- 第11回 難波ベアーズ 2020-04-09
- 第10回 静かすぎる日々 2020-04-01
- 第9回 ウタサ祭り 2020-02-19
- 第8回 東京 2020-01-12
- 第7回 2019年 2019-12-28
- 第6回 SHIBUYA全感覚祭 2019-10-28
- 第5回 Human Rebellion 2019-10-11
- 第4回 全感覚祭 大阪 2019-10-05
- 第3回 祭の前夜 2019-09-20
- 第2回 whose food? 2019-09-12
- 第1回 Future Values 2019-08-27
- 第0回 statement food 2019-08-27
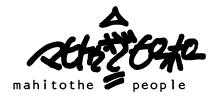 2009年、バンドGEZANを大阪にて結成。作詞作曲をおこないボーカルとして音楽活動開始。うたを軸にしたソロでの活動の他に、青葉市子とのNUUAMMとして複数のアルバムを制作。映画の劇伴やCM音楽も手がけ、また音楽以外の分野では国内外のアーティストを自身のレーベル十三月でリリースや、フリーフェスである「全感覚祭」を主催。中国の写真家Ren Hangのモデルをつとめたりと、独自のレイヤーで時代をまたぎ、カルチャーをつむいでいる。2019年、はじめての小説『銀河で一番静かな革命』(幻冬舎)を出版。GEZANのドキュメンタリー映画「Tribe Called Discord」がSPACE SHOWER FILM配給で全国上映。バンドとしてはFUJI ROCK FESTIVALのWHITE STAGEに出演。2020年、5th ALBUM「狂(KLUE)」をリリース、豊田利晃監督の劇映画「破壊の日」に出演。初のエッセイ集『ひかりぼっち』(イーストプレス)を発売。監督・脚本を務めた映画「i ai」が公開予定。
2009年、バンドGEZANを大阪にて結成。作詞作曲をおこないボーカルとして音楽活動開始。うたを軸にしたソロでの活動の他に、青葉市子とのNUUAMMとして複数のアルバムを制作。映画の劇伴やCM音楽も手がけ、また音楽以外の分野では国内外のアーティストを自身のレーベル十三月でリリースや、フリーフェスである「全感覚祭」を主催。中国の写真家Ren Hangのモデルをつとめたりと、独自のレイヤーで時代をまたぎ、カルチャーをつむいでいる。2019年、はじめての小説『銀河で一番静かな革命』(幻冬舎)を出版。GEZANのドキュメンタリー映画「Tribe Called Discord」がSPACE SHOWER FILM配給で全国上映。バンドとしてはFUJI ROCK FESTIVALのWHITE STAGEに出演。2020年、5th ALBUM「狂(KLUE)」をリリース、豊田利晃監督の劇映画「破壊の日」に出演。初のエッセイ集『ひかりぼっち』(イーストプレス)を発売。監督・脚本を務めた映画「i ai」が公開予定。





