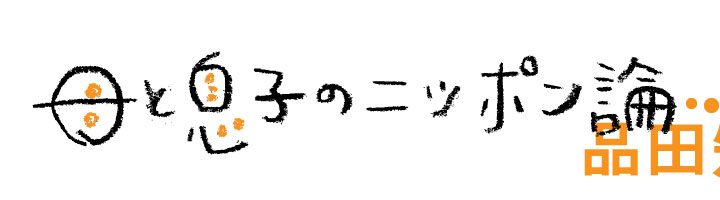母となった人の多くが「息子が可愛くてしょうがない」と口にする。手がかかればかかるほど、可愛いという。女性たちは息子のために、何を置いても尽くそうとする。それは恋人に対するよりも粘っこくて重たい心かもしれない。息子たちは、そんな母について、何を思っているのだろうか。そのような母に育てられた息子と、娘たちはどのように関係を作っているのだろうか。母と息子の関係が、ニッポンにおける人間関係の核を作り、社会を覆っているのではないのか。子育てを終えた社会学者が、母と息子の関係から、少子化や引きこもりや非婚化や、日本に横たわる多くの問題について考える。
母親業というものは、終わらないものなのでしょうか。私は一度ならず二度までも母親業を経験(息子と娘)したあと、今は廃業したと信じていました。しかし、周りはどうやらそうでもないらしいと近頃気づかされる機会がありました。ニッポンの母親たるもの、いつまでもその業から降りることなんてありえないらしいのです。ああ、なんたる過酷で、かつ甘美な業なのでしょうか、母親業というやつは。まるで幼い子どもがいた時と同じように、二十歳をすぎた子どもの様子をわがこととして語る女性たちを前にして考え込んでしまいました。私もかつてその輪の中にいて、さほど違和感を持たずにいたことも確かです。人生の一時期子育てに頭を悩ませ、文字通り忙殺された時期はあったものの、私にとって子育てはすぎさった嵐のようなのものです。
この連載では母親業を廃業したつもりだった社会学者として、母と息子の関係から日本社会を語ってみようと思います。
母と子は一心同体
かつて子育て法の変遷について本を書いたことがあります[1]品田知美,2004,子育て法革命:親の主体性をとりもどす,中公新書.。日本人の子育て法が、あまり望ましくない方向に変わりつつあることへの警鐘を含んでいたつもりでした。保育分野の専門家にも懸念を共有してくれた方々がいましたし、悩める母親たちからの反響もありました。そのなかに出演したTV番組の視聴者から届いた印象的なメールがあります。「息子の子育てで悩んでいる時に番組を見て、救われた。最後は自然と涙がでてしまうほど。」というものでした。あらためて追い詰められて頑張っている母親は本当に多いのだと感じました。番組のなかで、私はさほど特別な話をした記憶がなかったのですが、メールでは、「子どもが恥ずかしいことをしても我慢するのが親のつとめ」という言葉に助けられていると書かれていました。確かに日頃から周囲にもそう語っていたように思います。いえ、自らに言い聞かせてきた言葉であったのかもしれません。
母親とは違う個人である限り、してほしくないことをするのが子どもというものです。母親業とは恥ずかしさを飲み込み続ける修行の連続なのでした。息子がピカピカの小学校1年生になって初めての授業参観。彼はGジャンを着たまま授業を受けていました。積極的に手をあげていたのですが、その度にGジャンの袖に筆箱や教科書が引っかかり、机の下にバラバラと落ちるんです。静かな教室に苦笑がもれていました。あー、何やってるんだ息子!しかし担任の先生の対応は素晴らしかった。「〇〇くん、上着脱いだほうがいいかもね」とさらっと伝えてその場を収めてくれました。そこになんの非難の含みもありません。素敵な先生と人生最初の学校で息子が出会えたことにいまでも感謝しています。
そう、気をつけないとどうしても自分が格好よく見られたいからという理由で、理不尽に子どもに怒ってしまったりするのです。母親自身のための子育ては長い目で見て親子に望ましい関係をもたらさないと思います。『子どものことは子どもの責任で』[2]フランソワーズ・ドルト,2002,子どものことは子どもの責任で,みすず書房.とフランソワーズ・ドルトも説いているように、古今東西、親には子どもと自他の区別を忘れがちなところがあります。ただ日本の場合は、周囲からも子どもがしたことに対して、母親に責任を押し付けられることが多いのです。それでつい、母たちは子どもに「人様に迷惑をかけるな」と繰り返し諭したり謝ったりしながら過ごすことになります。母と子は一体であるとみなす空気がとてつもなく強力なので、頭でわかっていても「子どものことは子どもの責任で」と、念仏のように日々唱えていないと、その空気に飲まれてしまいそうになるのです。
ところで、不思議なことに母親たちは息子が自分に迷惑をかけてもまったく厭わず、あえて迷惑を被っているところがあります。古典的日本論の『菊と刀』[3]ルース・ベネディクト,1987,[定訳]菊と刀:日本文化の型,社会思想社.にも幼児期の男の子が母親を相手に癇癪玉を破裂させ、存分に攻撃を加えても許される様子が驚きとともに描かれていますが、そんな姿を現代でも目にすることが度々ありました。幼い頃から母親が自分にやってほしくないことを伝えれば、子どもは自ずと「人様に迷惑をかける」こととは何かを学ぶ機会を日常で与えられるなのに、母親たちはそうしていません。子どもはウチで「人様に迷惑をかける」こととは何かを学ぶ機会が足りません。子どもに身を挺して子育てすることが厭わず母と子は一心同体だと思っている限り、「子どもからの迷惑」という考え方は浮かんでこないでしょう。
『子育て法革命』が出版されてからも、母と子の関係性をめぐる潮流にはほとんど変化がありませんでしたし、母親業はさらに期待値の大きい稼業となっているようです。どうしてこうなってしまうのでしょうか。そこであらためて、母と息子の関係が国のかたちをうみだす重要な源泉ではないかと疑いはじめました。日本社会を成り立たせている根源的なるものの一つに、母と息子の関係性があるとするならば、なぜそうなっているのかを考えていきたいと思うのです。この国を語るとき母親への感謝はいつも語られるのですが、その困惑について、もう少し語られてもよいでしょう。
重たい母親業
ここ5年ほどは保育士・幼稚園教諭養成系の大学教員として働いていました。学生だけではなく保護者とも接点の多いなかで、あらためて痛切に感じたのは、子どもからみたニッポンの母親たちの重さです。もう成人した子どもたちの人生であるはずなのに、母の意向は子どもに常に忖度されていました。きっと母親たちは自分がそこまで子どもを縛っているとは思っていないでしょう。専攻の選び方から就職にいたるまで、学生たちは母親の希望をどう取り入れていけばよいのか、自分の希望との間で悩んでいました。それは、現代の子どもが必ずしも抱えなくてもよい悩みのはずなのに。大学とは子どもとして過ごしてきた学生を、社会に大人として送り出すという離れ業を期待されている場でもあります。結果的にはそろそろ子ども業を終えたがっている学生を支援して、母親業を続けたがっている保護者に廃業へと向かってもらうことも教員の仕事の一部となっていました。つまるところ、母親業が終わってくれないとと子ども業も終わらせることができないからです。
保育士や幼稚園教諭というお仕事とは、卒業と同時に学生に大人であることを強く迫る職業でもあります。無邪気に子どもと遊ぶことが仕事であると勘違いしている人もいるでしょうけれども、そうではありません。子どもの命を預かる職業だからです。人は乳幼児を前にして、大学で積み上げた知識だけをもとにした行動で対応することなどできません。ホテルの受付のような対人サービス業と、人を育てる保育業には大いなる違いがあるのです。結局、保育士不足が嘆かれるけれど、それは親不足(少子化!)と同じものだということです。母親業が重たいのであれば、代替の人手を提供しようとする保育業も重たい職業となるのは必然です。しかも重さに見合った賃金は支払われません。母親という無償で子どもを育ててくれる奇特な人が多数いる限り、保育者も崇高な理念のもと、薄給で働くことを当然視されがちです。子どもを育てる重たさに躊躇して母親業に参入しようとする人が少ない時代、人手は施設の内でも外でも不足することになります。
さらに、幼い頃からの人の育つ環境の重要性は近年あらためて注目されています。例えばノーベル賞経済学者ヘックマンによる『幼児教育の経済学』[4]ジェームズ・J・ヘックマン,2015,幼児教育の経済学,東洋経済新報社.のような本が話題となりました。ヘックマンによれば、乳幼児への質の良い教育(保育)こそが、長い人生をよく歩んでいくために必要なスキルを、長期的にみて少ない費用で提供すると実証されたとのことです。こういう議論が日本に入ってくると、さらに輪をかけて母親業が重たくなりそうで心配になります。例えばヘックマンはこの著書で「子供たちを一室に閉じこめて質の悪い全日保育を施せば、かえって害になりかねない」と述べているのです。「子どもを保育園に預けて働くなんてとんでもない」と、親族から厳しい視線をむけられた経験のある大卒女性は、私を含めて多いと思います。初めて母親になった人が躊躇しないで仕事を続けようとしても、周囲の支えどころか厳しい目線すら投げかけられることさえあるのが現代日本です。結果として、大卒女性が子どもを持つと無業となりやすい傾向が長らくありました。
現政権が熱意を傾けているように、「この国」を本気で変えようとする時、偽政者は幼いころの育ちに照準し、家庭教育や幼児教育を掌握しようとします。その意図とあいまって、すでに重たい荷物を背負わされている母親たちに、さらなる荷物が積み上げられようとしているように思います。事実、母親の育児時間はここ数十年間ずっと増え続けているのです[5]品田知美,2016,松信ひろみ編,家族の生活時間とワークライフバランス,近代家族のゆらぎと新しい家族のかたち[第2版].。その一方で、母親業をこなせずに虐待してしまう親も後を絶たず、里親希望者は伸び悩んでいます。子育て稼業の大変さを誰もが受け止めきれていません。
「ふがいない息子」の近代
ところでなぜ、母と息子から語ろうとするのでしょうか。
上野千鶴子氏によれば、身分や地位が移動可能であると信じられるようになった近代になって「ふがいない息子」と「不機嫌な娘」が産み出されました[6]上野千鶴子,1997,日本の母の崩壊,平川祐弘・萩原孝雄編,日本の母:崩壊と再生, 新曜社.。理由は明らかで、地位が固定されている前近代であれば、息子が父のような身分となることがあらかじめ定まっているので、「ふがいない息子」は存在しようもないからです。「大きくなったら何になるの?」という問いを子どもたちが持つこともなく、母親も期待しようもない時代が前近代です。一方、「不機嫌な娘」は、夫を選択できる時代なのに魅力的とはいえない結婚をした母に対して、「まちがった選択をした」責任を免罪しないことから出現します。
ようやく「不機嫌な娘」たちは、母と娘の問題に対して目に見える書き手として登場しはじめました。けれど、「ふがいない息子」が積極的な発言をしている様子はありません。それは自らの弱さを白日のもとにさらすことになる作業となり、「不機嫌な娘」の告発のように堂々とはいかないでしょう。
では「ふがいない息子」と逆の「立派な息子」とは誰なのでしょうか。現代日本でその認識枠は驚くほど単純です。端的に言って「立派な息子」とはよい大学に入りよい就職をする息子なのです。あるいは、スポーツや資格試験など競争に打ち勝ってよい地位に上り詰めた者たちのことです。しかし、よい大学もよい就職もそうですけれど地位とは相対的なものなので、全員がその椅子に座ることはないわけです。まして昨今はそこに娘たちも参入しようとしているのですから、争いは熾烈になります。その競争への参入意欲を持つ母親が、息子に投入する時間や金銭的資源を知ると本当に驚くほどです。投入する時間や金銭などひねり出すことができない家庭で育つ子どもたちとの差は開くばかりでしょう。公教育は自前で学力をつけることに失敗していますから、高学歴の母親たちが自分の息子を「立派に」することに照準して、自ら教えたり熱心に情報収集をし、塾や家庭教師をつけて受験競争を支援したら、貧しい家庭の子どもが太刀打ちできるとは到底思えません。
人が一律に並べられる時「立派な息子」がいるならば、必ず「ふがいない息子」も存在します。学校教育の現場では「オンリーワン」の個性を強調する言説が繰り返され続ける時代に、母親からして、いや母親こそが相変わらず一律に並べたがっているようにさえみえます。見事な逆転現象ではないでしょうか。
だからこそ「立派な息子」たちであろうとする男性はその地位を女性に譲り渡さないよう、死守するのでしょう。男女雇用機会均等法が施行された1986年からすでに30年がすぎましたけれど、日本女性の社会的地位は惨憺たる状況にあります。例えば、2016年版「ジェンダー・ギャップ指数(Gender Gap Index:GGI)」でデータがそろった144カ国中日本は111位で、前年よりも後退さえしています。地位の奪い合いのもとで、女性が排除されつづける理由は、自らの地位を確保することよりも母親業に熱意を傾けて息子の地位達成を重視した母親たちが背後にいるからでもあるのです。一昔前であれば責任の一端を女性に問うことはできなかったかもしれませんが、もうそんな言い訳ができる時代は過ぎ去ったのではないでしょうか。いまや個人を生きようとする女性には、息子に不平等に肩入れする母親たちという、敵が対峙しているとすらこの頃感じています。
息子愛と少子化
それにしても、子育て中、息子が可愛くてしょうがない、というセリフを何度聞いたことでしょう。正直にいって私にはよくわかりませんでした。息子であろうが、娘であろうが、その感情に代わり映えはなかったからです。繰り返し母親たちからそんなセリフを聞かされるうち、この“息子愛”には現代日本の少子化ぶりという謎を解く、重大な鍵が隠されているんじゃないか、と思い始めました。性差を意識した子育ての意図せざる結果が、男女のミスマッチをもたらすと思うのです。
母親たちがいうには「男の子って、手がかかるよね」「ちっともしっかりしない」「いつまでたっても幼い」。だから可愛いというのです。それは、因果関係が逆で、母親がいつまでも息子に手をかけすぎるから、子どもは自立しないのではないでしょうか。幼い時の発達に性差が見出されることはもちろんあります。でも、人は子どもが生まれ落ちた瞬間から性差を意識した子育てをする傾向があることもよく知られています。見出される性差が遺伝的なものなのか、現在知られつつあるエピジェネティクスなものなのか、周囲の働きかけによる環境的なものなのか弁別することは容易ではありません。それにしても、巷の本屋をみても「男の子/女の子」を区別した育児本は相変わらず並んでいますし、性差を意識して親は子育てをしているという研究結果も多数あります。日頃から性差別に敏感なはずの大卒キャリア女性たちでさえ、「男の子は、これだから困る」とちょっぴり嬉しそうに語ります。性差を意識した子育てをしていることに、気づいていないのでしょう。
そのためなのでしょうか、いつまでも幼いと可愛がられる男の子の傍らで、どちらかといえば女の子はさっさと自立して母親に憎まれ口を言い始めます。思春期の母娘の葛藤が時に激しくなりがちなのは世界中で語られていますけれど、日本では別水準の葛藤があるように思います。なぜなら、娘の側からみて不当な差別を日本の母親たちは今もしているからです。娘を下宿を要する大学に行かせなかったり、4年生大学でなく短期大学や専門学校にするよう促したりすることはよくあります。現在でも4年生大学進学率は男子より女子の方が低いままです。地方大学には、水準に見合わない学業優秀な女性が数多くいることを教員たちは知っています。親に性差別された怨嗟は、時にきょうだい間の憎悪に結びついたり精神的な病の元になっていることもあるでしょう。こじれた母娘問題は急速に白日のもとにさらされつつあります。その裏で母息子の関係性はひっそりと隠されているのです。その痛々しい例がひきこもりの息子たちではないでしょうか。
こんなふうに「不機嫌な娘」と「ふがいない息子」として育てられた子どもたちが、次世代にカップルとなり関係性を維持できるとは思えません。母親たちは手のかかる息子たちに、自分のかわりに世話をしてくれる女性を求めます。でも、たいがいの娘たちはもうそんなことをしないでしょう。そして、いまのところ日本での結婚は男が「立派な息子」でないと好まれないようなので、「ふがいない息子」たちの結婚相手はなかなかみつかりません。かくして息子愛は未婚化に寄与し、子どもは減り続けてしまうのです。
* * * * * * * * * * * *
永遠にお世話し続けなくてはいけない男の子こそが、心の恋人である母親たち。一昔前にいた手のかかる夫はだいぶ少なくなりました。そしてたいがい不在がちです。そんな時代、彼女たちの眼差しは息子に注がれます。歴史を振り返っても日本女性は、母である限り強い立場にありつづけることができました。秀吉亡きあと豊臣秀頼の母として淀殿は政治に介入し続けました。女性は立派な地位にある息子の母であるとき、権力を手に入れてきたのです。そして母と息子は文字通り命運を共にしてきました。
しかしついに現代日本では、女性には2つめの道が開かれつつあります。自らが直接社会で権力を手にする道です。そのとき、女性はどちらを選ぼうとするのでしょうか。どう転ぶのかわからない息子に肩入れするよるも、自らが社会で地位を得て活躍しようとするほうが手っ取り早いと考えるかもしれません。母親の息子への愛は多くの映画やドラマで描かれてきたように、無私の心から来ているものではなく、ほんとうは母親自身の下克上をかけた戦いでもあったのではないでしょうか。平等な社会が整ってきた時にこそ、母が息子に託してきた真の願いが露わになります。
次回からは、そんな母と息子のあいだに潜んでいる関係性に様々な事象から光をあて、ニッポン社会というシステムの一端を紐解いていきたいと思います。
注[+]
Profile

1964年、三重県尾鷲市生まれ、愛知県で育つ。早稲田大学卒業後、シンクタンク勤務をへて東京工業大学大学院修了。博士(学術)、社会学者。現在、早稲田大学文学学術院ほか非常勤講師。主な著書に『子育て法革命』(中央公論新社)、『家事と家族の日常生活:主婦はなぜ暇にならなかったのか』(学文社)、「平成の家族と食」(晶文社)など。