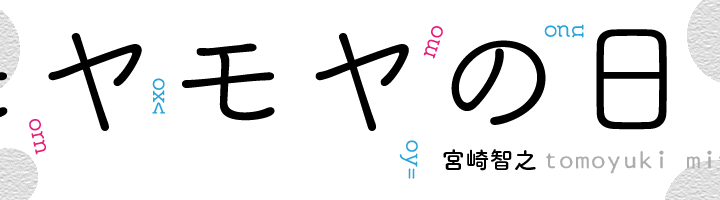僕の幼馴染みにY君という男がいる。かれこれ33年の付き合いになる。おそらく家族以外で一番多くの時間を一緒に過ごしてきたのは、このY君ではないか。いや、もしかしたら家族よりも長い時間を共にしているかもしれない。その時間のほとんどが、素晴らしく不毛なものだった。
Y君は人間の愚かさを凝縮したような人間で、つまり僕とまったく同じなのである。実はこの連載にもすでに何度か登場していて、Y君と最初に出会ったのは、彼がサッカーのゴールネットに絡まって動けなくなっていたときだし、「好きな人と一緒にいられるのが一番でモテる必要はない」と言う僕に、「『モテる人が好きな人』を好きになった場合はどうするんだ?」と訊いてきたのもY君だった。Y君の愚かさは身も蓋もない部分があり、前述のような質問をされたとき、僕は頭をフル回転させる。ときにはY君を説得しようと、多様な比喩や隠喩、例え話を繰り出して臨むが、なかなかY君の首を縦に振らせることができない。
Y君は僕の鏡であり、Y君の愚かさは僕の愚かさでもあるため、Y君を説得するという営みは、自分を説得するという営みでもある。それによって、僕の語彙力は格段にアップした。文章を書くときも、「これではYは納得しないだろう」とY君にまったく関係ないにもかかわらず、僕の中のY君チェックが勝手に入って、愚か者の僕とY君でも肯けるように書き直したりする。僕はなにをしているのだろうか。
そんなY君の有名なエピソードに、「It's a small town(イッツ ア スモール タウン)」というものがある。20代前半のある日、僕はY君と一緒に飲んでいた。その店は東京の奥の奥、僕たちの故郷である東京都福生市にあって、美味しいお酒が飲めるうえに、手作りの定食まで出してくれる。しかも木材を基調とした店内には和風のアンティーク感が漂っており、それはそれはとてもお洒落な店なのである。
この店を教え、その日はじめて来店したY君は、ご機嫌そのものだった。「いい店を教えてくれてありがとうな!」と顔をほころばせていた。僕らは千鳥足になりながら笑顔でその日は早い時間に別れた。
翌日、僕はまたその店の定食が食べたくなり、二日連続で通った。晩酌がてら、「白身魚のフライ定食」を食べていると、ドアが勢いよく開く音が聞こえた。そして入り口からY君が颯爽と入ってきた。女性が一緒だった。僕の知らない女性である。Y君は「ここ俺ちゃんの行きつけなんだ」みたいな雰囲気を漂わせて、女性を案内していた。ここで声をかけるのも野暮だというものだが、なにせ、店内はそんなに広くない。気づかないふりをするのは無理がありすぎる狭さである。僕は手を軽く上げて、「おお、Yじゃないか」と声を掛けた。
その瞬間の凍りついたY君の表情を、僕は生涯忘れることができない。Y君の隣にいた女性が「友達?」とY君に訊いた。するとY君は欧米の人がするような、手のひらを上にあげる「やれやれ」のジェスチャーをしながら、「狭い街だからね」と言った。僕は、「やれやれ」のジェスチャーをリアルでしている人間を、このとき初めて見た。その後、Y君はペースを乱したのか、常にそわそわしながら女性と食事しており、僕より先にお会計を済ませてしまった。そして最後に僕のところに来て、「おい、たまには飲もうぜ」と言ったのだった。
これが「It's a small town」のすべてである。ちなみに、僕のせいではないと思うが、Y君はその女性とうまくいかなかったらしい。それにしても仮にうまくいったとして、その後、僕のことを女性にどう紹介するつもりだったのだろうか。とりあえず対症療法で乗り切ろうと画策する愚かさが、僕そっくりである。
先ほど、このコラムを書きたくて、Y君に許可を取ろうとLINEで連絡した。「まったく問題ない。好きなように書いてくれ」とのことだった。げに潔い愚か者である。愚かだけど、なぜだか愛おしい。
Back Number
- 第251回 大晦日の大晦日感(2)
- 第250回 高級な蜜柑(3)
- 第249回 人生の杭
- 第248回 コーヒーの香り
- 第247回 はじめてのサンタクロース
- 第246回 犬と赤子
- 第245回 手紙
- 第244回 僕が好きだったもの
- 第243回 クリエイティブ迷子
- 第242回 懐かしさ
- 第241回 年末進行
- 第240回 二代目・朝顔観察日記(完)
- 第239回 ビニール傘
- 第238回 赤子の習い事
- 第237回 短眠
- 第236回 褒めて伸ばす
- 第235回 コンビニのKさん
- 第234回 風船トレーニング
- 第233回 吾輩は僕である
- 第232回 電話で伝える氏名の漢字
- 第231回 ロクちゃんのぬいぐるみ
- 第230回 書籍化
- 第229回 今日は何の日
- 第228回 本の片付けについて(3)
- 第227回 二代目・朝顔観察日記(8)
- 第226回 育児について
- 第225回 文学フリマ
- 第224回 僕が走った
- 第223回 大学を卒業できない夢
- 第222回 読書の悦楽
- 第221回 ウニについて
- 第220回 駄目貯金術
- 第219回 なにもない世界
- 第218回 シックスマン
- 第217回 老い
- 第216回 赤爆
- 第215回 好き嫌い
- 第214回 3日前の晩ご飯
- 第213回 千葉の沼
- 第212回 前髪のこと(2)
- 第211回 積読くずし
- 第210回 疲れを知ること
- 第209回 動物園
- 第208回 出口がある街
- 第207回 前髪のこと
- 第206回 観光地のマグネット(3)
- 第205回 覚え違いタイトル集
- 第204回 小さな一歩、大きな一歩
- 第203回 寒い季節のアイス
- 第202回 徹夜について
- 第201回 観光地のマグネット(2)
- 第200回 行けたら行く
- 第199回 狭い街
- 第198回 二代目・朝顔観察日記(7)
- 第197回 マスクチェーン(2)
- 第196回 観光地のマグネット
- 第195回 偶然の駄洒落(2)
- 第194回 地震
- 第193回 勉強
- 第192回 家賃の振り込み(2)
- 第191回 二代目・朝顔観察日記(6)
- 第190回 犬年齢
- 第189回 やりたいことリスト
- 第188回 二つ名
- 第187回 二代目・朝顔観察日記(5)
- 第186回 モテとは何か
- 第185回 怪談プリンター
- 第184回 筋トレ嫌い(2)
- 第183回 メロトッツォ
- 第182回 犬の誕生日
- 第181回 彼岸花
- 第180回 赤子が強い
- 第179回 赤子の苛立ち
- 第178回 今日からおじさん
- 第177回 最近のニコル
- 第176回 二代目・朝顔観察日記(4)
- 第175回 親に似る
- 第174回 スティーヴ・アオキ
- 第173回 偶然の駄洒落
- 第172回 下北沢
- 第171回 コロナ以後
- 第170回 ダンス動画
- 第169回 フィルムを貼る仕事
- 第168回 優しい死神
- 第167回 自分の声
- 第166回 二代目・朝顔観察日記(3)
- 第165回 凪を生きる
- 第164回 高身長
- 第163回 黒マスク
- 第162回 二代目・朝顔観察日記(2)
- 第161回 マスクチェーン
- 第160回 痛いと言っていい
- 第159回 あいつは?
- 第158回 文化系トークラジオLife
- 第157回 父と中原中也
- 第156回 二代目・朝顔観察日記(1)
- 第155回 朝顔観察日記(6)〜あきらめない
- 第154回 ある夏の思い出
- 第153回 ワクチン接種2回目(5日目)
- 第152回 腰が痛い人
- 第151回 ピスタチオ
- 第150回 ワクチン接種2回目(2日目)
- 第149回 ワクチン接種2回目
- 第148回 ニコルゾーン
- 第147回 赤子はすごい(2)
- 第146回 退屈さ
- 第145回 髪を切りたい
- 第144回 日傘がほしい
- 第143回 4連休
- 第142回 文字入りTシャツ
- 第141回 本物を見ること
- 第140回 早朝の散歩
- 第139回 回復
- 第138回 ワクチン接種1回目(3日目)
- 第137回 ワクチン接種1回目(その後)
- 第136回 ワクチン接種1回目
- 第135回 朝顔観察日記(5)
- 第134回 あるひとつの日常
- 第133回 七夕の願い事
- 第132回 ありのまま、今、起こったことを書くぜ
- 第131回 気になる投票所
- 第130回 名選手、名監督にあらず
- 第129回 家賃の支払い
- 第128回 1年の折り返し
- 第127回 朝顔観察日記(4)
- 第126回 計画の大切さ
- 第125回 未来からの前借り
- 第124回 赤子の躍進
- 第123回 本の片付けについて(2)
- 第122回 歴史の分岐点
- 第121回 マリトッツォ
- 第120回 朝顔観察日記(3)
- 第119回 ラーミアンでバーメン
- 第118回 ためらい
- 第117回 冷房の設定温度
- 第116回 犬の帰還
- 第115回 弱音
- 第114回 ニコルの人気
- 第113回 紫陽花
- 第112回 風邪予報士
- 第111回 バンドマン(2)
- 第110回 雨のことば
- 第109回 朝顔観察日記(2)
- 第108回 祝日がない月
- 第107回 朝顔観察日記
- 第106回 心のなかの仄暗い場所
- 第105回 駄目さが希望
- 第104回 神隠しの犯人
- 第103回 最高の海外旅行
- 第102回 生まれて初めて
- 第101回 怪談タクシー
- 第100回 目出度い
- 第99回 筋トレ嫌い
- 第98回 1時間10分のモヤモヤ
- 第97回 寝てない自慢
- 第96回 朝一の僥倖
- 第95回 慎重さ
- 第94回 断酒(2)
- 第93回 「まだ生きている」
- 第92回 あいみょん
- 第91回 赤いカーネーション
- 第90回 応援しがい
- 第89回 連休明け
- 第88回 運転免許
- 第87回 読書
- 第86回 気圧のせい
- 第85回 人間は弱い
- 第84回 ダンゴムシを見つける達人
- 第83回 赤子はすごい
- 第82回 やさしくなりたい
- 第81回 ニコルのこと
- 第80回 サークルの夏合宿
- 第79回 ピアノを習っている男子
- 第78回 英雄・コービー
- 第77回 うぐいすの初鳴日
- 第76回 ナ、ノ、ハ、ナ
- 第75回 「されている」
- 第74回 スマホの充電ケーブルが溜まる件
- 第73回 人生で最高に幸福な時間
- 第72回 双子のライオン堂の竹田さん
- 第71回 お洒落な部屋着
- 第70回 白くて丸いやつ
- 第69回 キャズム超え
- 第68回 原稿の提出方法
- 第67回 イノベーション
- 第66回 やる気
- 第65回 コンプレックス
- 第64回 桜ばな
- 第63回 目黒の秋刀魚
- 第62回 角さんの分類
- 第61回 本の片付けについて
- 第60回 春はすごい
- 第59回 マスクは大事
- 第58回 3つ目のブルガリアヨーグルト
- 第57回 「愛犬家はみんな、うちの犬が一番可愛いと思っている説」
- 第56回 断酒
- 第55回 3月生まれ
- 第54回 「誰かが褒めていなければ褒めにくい問題」
- 第53回 10年前
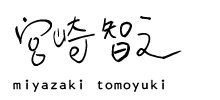 1982年生まれ、東京都出身。フリーライター。著書『モヤモヤ
1982年生まれ、東京都出身。フリーライター。著書『モヤモヤ
Twitter: @miyazakid