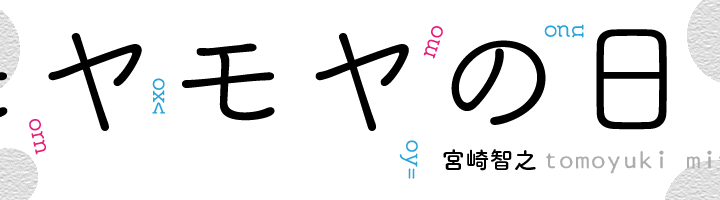腰痛がすっかりおさまった。しばらく前から腰痛のない生活を送っていて、赤子や犬と遊ぶ際もおっかなびっくりしなくて済むようになった。それにしても人間(とくに僕)とは忘れっぽい生き物である。あれだけ痛かったのだから、身体のどこかがどうにかなっていたに違いないのだ。せめて一度くらいは医者に行くべきだとは思うのだが、痛みがなくなった途端、あれだけ痛かった感覚をすっかり忘れてしまい、足を運ぶのが億劫になっている。そしてまたいつか腰痛になる。
僕は忘れっぽい。亡くなった父も同様に忘れっぽかった。まだ元気だった頃、「おい、お前。この前のあれのあれはどうなってるんだ? ちゃんとあれしたのか?」と訊ねられたとき、さすがにそれは適当すぎると呆れたものだが、最近では父と似たようなことを言っている。「頑張らないと親に似る」という、マキタスポーツがTBSラジオ「東京ポッド許可局」で放った名言が胸に響く。
私生活でなら多少忘れっぽくても構わないのだけど、仕事ではそうはいかない。手帳に細かく仕事の予定を書く几帳面さもない。というか、たとえ書いたとて、僕は僕の汚い文字が読めないのだから仕方ない。しかし、父の時代と違うのは、今は高度なデジタル社会なのである。僕は仕事の予定が決まるやいなや、MacBook ProかiPhoneからGoogleカレンダーに書き込む。いくらでも細かく書き込めるし、前日や直前には通知をくれる。Googleがなくなったら、僕は明日からなにをすればいいのかわからない。完全に依存しているけど、なければ生きられないのである。
今朝、寝室でベッドに寝転がっていると赤子(1歳3か月、息子)が来て、「あぷあぷあぷ」と言いながら、マットレスをバンバンと叩き出した。僕は「赤ちゃんが来た! 赤ちゃんが来た!!」と叫び、赤子をベッドまで引き上げた。一瞬、腰に嫌な感覚が走った。赤子を抱えながら腰を慎重に動かしてみたが異常はないようだ。はやく病院に行く日を決めてGoogleカレンダーに書き込まなければいけないと思いつつ、それすら忘れそうな僕はどうすればいいのだろうと途方に暮れるのであった。
Back Number
- 第251回 大晦日の大晦日感(2)
- 第250回 高級な蜜柑(3)
- 第249回 人生の杭
- 第248回 コーヒーの香り
- 第247回 はじめてのサンタクロース
- 第246回 犬と赤子
- 第245回 手紙
- 第244回 僕が好きだったもの
- 第243回 クリエイティブ迷子
- 第242回 懐かしさ
- 第241回 年末進行
- 第240回 二代目・朝顔観察日記(完)
- 第239回 ビニール傘
- 第238回 赤子の習い事
- 第237回 短眠
- 第236回 褒めて伸ばす
- 第235回 コンビニのKさん
- 第234回 風船トレーニング
- 第233回 吾輩は僕である
- 第232回 電話で伝える氏名の漢字
- 第231回 ロクちゃんのぬいぐるみ
- 第230回 書籍化
- 第229回 今日は何の日
- 第228回 本の片付けについて(3)
- 第227回 二代目・朝顔観察日記(8)
- 第226回 育児について
- 第225回 文学フリマ
- 第224回 僕が走った
- 第223回 大学を卒業できない夢
- 第222回 読書の悦楽
- 第221回 ウニについて
- 第220回 駄目貯金術
- 第219回 なにもない世界
- 第218回 シックスマン
- 第217回 老い
- 第216回 赤爆
- 第215回 好き嫌い
- 第214回 3日前の晩ご飯
- 第213回 千葉の沼
- 第212回 前髪のこと(2)
- 第211回 積読くずし
- 第210回 疲れを知ること
- 第209回 動物園
- 第208回 出口がある街
- 第207回 前髪のこと
- 第206回 観光地のマグネット(3)
- 第205回 覚え違いタイトル集
- 第204回 小さな一歩、大きな一歩
- 第203回 寒い季節のアイス
- 第202回 徹夜について
- 第201回 観光地のマグネット(2)
- 第200回 行けたら行く
- 第199回 狭い街
- 第198回 二代目・朝顔観察日記(7)
- 第197回 マスクチェーン(2)
- 第196回 観光地のマグネット
- 第195回 偶然の駄洒落(2)
- 第194回 地震
- 第193回 勉強
- 第192回 家賃の振り込み(2)
- 第191回 二代目・朝顔観察日記(6)
- 第190回 犬年齢
- 第189回 やりたいことリスト
- 第188回 二つ名
- 第187回 二代目・朝顔観察日記(5)
- 第186回 モテとは何か
- 第185回 怪談プリンター
- 第184回 筋トレ嫌い(2)
- 第183回 メロトッツォ
- 第182回 犬の誕生日
- 第181回 彼岸花
- 第180回 赤子が強い
- 第179回 赤子の苛立ち
- 第178回 今日からおじさん
- 第177回 最近のニコル
- 第176回 二代目・朝顔観察日記(4)
- 第175回 親に似る
- 第174回 スティーヴ・アオキ
- 第173回 偶然の駄洒落
- 第172回 下北沢
- 第171回 コロナ以後
- 第170回 ダンス動画
- 第169回 フィルムを貼る仕事
- 第168回 優しい死神
- 第167回 自分の声
- 第166回 二代目・朝顔観察日記(3)
- 第165回 凪を生きる
- 第164回 高身長
- 第163回 黒マスク
- 第162回 二代目・朝顔観察日記(2)
- 第161回 マスクチェーン
- 第160回 痛いと言っていい
- 第159回 あいつは?
- 第158回 文化系トークラジオLife
- 第157回 父と中原中也
- 第156回 二代目・朝顔観察日記(1)
- 第155回 朝顔観察日記(6)〜あきらめない
- 第154回 ある夏の思い出
- 第153回 ワクチン接種2回目(5日目)
- 第152回 腰が痛い人
- 第151回 ピスタチオ
- 第150回 ワクチン接種2回目(2日目)
- 第149回 ワクチン接種2回目
- 第148回 ニコルゾーン
- 第147回 赤子はすごい(2)
- 第146回 退屈さ
- 第145回 髪を切りたい
- 第144回 日傘がほしい
- 第143回 4連休
- 第142回 文字入りTシャツ
- 第141回 本物を見ること
- 第140回 早朝の散歩
- 第139回 回復
- 第138回 ワクチン接種1回目(3日目)
- 第137回 ワクチン接種1回目(その後)
- 第136回 ワクチン接種1回目
- 第135回 朝顔観察日記(5)
- 第134回 あるひとつの日常
- 第133回 七夕の願い事
- 第132回 ありのまま、今、起こったことを書くぜ
- 第131回 気になる投票所
- 第130回 名選手、名監督にあらず
- 第129回 家賃の支払い
- 第128回 1年の折り返し
- 第127回 朝顔観察日記(4)
- 第126回 計画の大切さ
- 第125回 未来からの前借り
- 第124回 赤子の躍進
- 第123回 本の片付けについて(2)
- 第122回 歴史の分岐点
- 第121回 マリトッツォ
- 第120回 朝顔観察日記(3)
- 第119回 ラーミアンでバーメン
- 第118回 ためらい
- 第117回 冷房の設定温度
- 第116回 犬の帰還
- 第115回 弱音
- 第114回 ニコルの人気
- 第113回 紫陽花
- 第112回 風邪予報士
- 第111回 バンドマン(2)
- 第110回 雨のことば
- 第109回 朝顔観察日記(2)
- 第108回 祝日がない月
- 第107回 朝顔観察日記
- 第106回 心のなかの仄暗い場所
- 第105回 駄目さが希望
- 第104回 神隠しの犯人
- 第103回 最高の海外旅行
- 第102回 生まれて初めて
- 第101回 怪談タクシー
- 第100回 目出度い
- 第99回 筋トレ嫌い
- 第98回 1時間10分のモヤモヤ
- 第97回 寝てない自慢
- 第96回 朝一の僥倖
- 第95回 慎重さ
- 第94回 断酒(2)
- 第93回 「まだ生きている」
- 第92回 あいみょん
- 第91回 赤いカーネーション
- 第90回 応援しがい
- 第89回 連休明け
- 第88回 運転免許
- 第87回 読書
- 第86回 気圧のせい
- 第85回 人間は弱い
- 第84回 ダンゴムシを見つける達人
- 第83回 赤子はすごい
- 第82回 やさしくなりたい
- 第81回 ニコルのこと
- 第80回 サークルの夏合宿
- 第79回 ピアノを習っている男子
- 第78回 英雄・コービー
- 第77回 うぐいすの初鳴日
- 第76回 ナ、ノ、ハ、ナ
- 第75回 「されている」
- 第74回 スマホの充電ケーブルが溜まる件
- 第73回 人生で最高に幸福な時間
- 第72回 双子のライオン堂の竹田さん
- 第71回 お洒落な部屋着
- 第70回 白くて丸いやつ
- 第69回 キャズム超え
- 第68回 原稿の提出方法
- 第67回 イノベーション
- 第66回 やる気
- 第65回 コンプレックス
- 第64回 桜ばな
- 第63回 目黒の秋刀魚
- 第62回 角さんの分類
- 第61回 本の片付けについて
- 第60回 春はすごい
- 第59回 マスクは大事
- 第58回 3つ目のブルガリアヨーグルト
- 第57回 「愛犬家はみんな、うちの犬が一番可愛いと思っている説」
- 第56回 断酒
- 第55回 3月生まれ
- 第54回 「誰かが褒めていなければ褒めにくい問題」
- 第53回 10年前
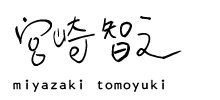 1982年生まれ、東京都出身。フリーライター。著書『モヤモヤ
1982年生まれ、東京都出身。フリーライター。著書『モヤモヤ
Twitter: @miyazakid