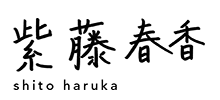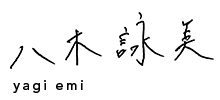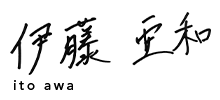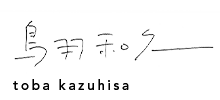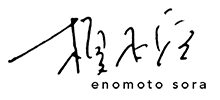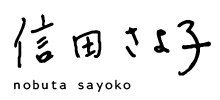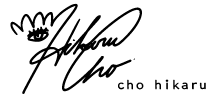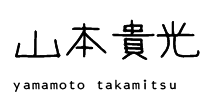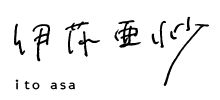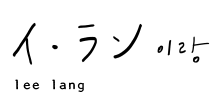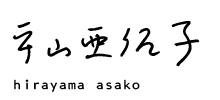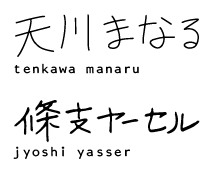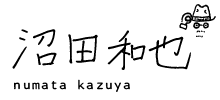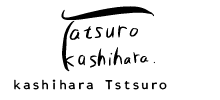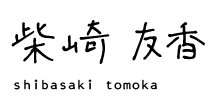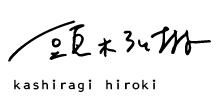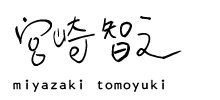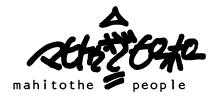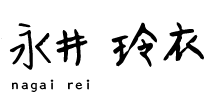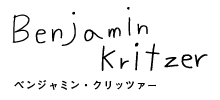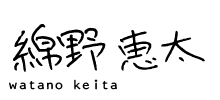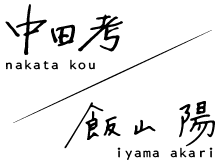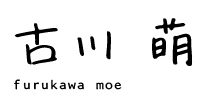膝の皿を金継ぎ
- 第8回 2月の日記(後半) 2024-03-28
- 第7回 2月の日記(前半) 2024-02-27
- 第6回 わからなさとの付き合い方 2024-01-29
- 第5回 サバイバル煮物 2023-12-28
- 第4回 ところでペットって飼ってます? 2023-11-30
- 第3回 喋る猫はいなくても 2023-10-31
- 第2回 夢のPDCA 2023-09-29
- 第1回 ここではない、青い丸 2023-08-31
アワヨンベは大丈夫
- 第9回 ごきげんよう(前編) 2024-04-18
- 第8回 ウサギ小屋の主人 2024-03-17
- 第7回 竹下通りの女王 2024-02-15
- 第6回 ママの恋人 2024-01-11
- 第5回 Nogi 2023-12-11
- 第4回 セイン・もんた 2023-11-15
- 第3回 私を怒鳴るパパの目は黄色だった 2023-10-13
- 第2回 宇宙人とその娘 2023-09-11
- 第1回 オール・アイズ・オン・ミー 2023-08-11
旅をしても僕はそのまま
- 第5回 アシジと僕の不完全さ 2024-01-27
- 第4回 ハバナのアルセニオス 2023-11-15
- 第3回 スリランカの教会にて 2023-09-16
- 第2回 クレタ島のメネラオス 2023-06-23
- 第1回 バリ島のゲストハウス 2023-05-31
おだやかな激情
- 第11回 なめらかな過去 2024-04-04
- 第10回 ちぐはぐな部屋 2024-03-05
- 第9回 この世の影を 2024-02-02
- 第8回 映したりしない 2024-01-11
- 第7回 とばされそうな 2023-12-04
- 第6回 はらはら落ちる 2023-11-01
- 第5回 もしもぶつかれば 2023-10-02
- 第4回 つややかな舌 2023-09-02
- 第3回 鴨になりたい 2023-08-01
- 第2回 かがやくばかり 2023-07-04
- 第1回 いまこのからだで目に映るもの 2023-05-31
- 第4回 うまくいかなくても生きていく──『十二月の十日』ジョージ・ソーンダーズ 2023-09-25
- 第3回 元恋人の結婚式を回避するために海外逃亡──『レス』アンドリュー・ショーン・グリア 2023-04-21
- 第2回 とにかく尽くし暴走する、エクストリーム片思い──『愛がなんだ』角田光代 2023-01-17
B面の音盤クロニクル
- 第8回 その日はあいにく空いてなくてね──Bobby Charles, “Save Me Jesus” 2024-03-08
- 第7回 クリスマスのレコードはボイコットする 2023-12-22
- 第6回 とうとう会得した自由が通底している 2023-05-06
- 第5回 あれからジャズを聴いている理由──”Seven Steps to Heaven” Feat. Herbie Hancock 2023-04-04
- 第4回 「本質的な簡素さ」の歌声──Mavis Staples “We’ll Never Turn Back” 2023-03-01
- 第3回 我が家にレコードプレイヤーがやってきた──Leon Redbone “Double Time” 2023-01-08
- 第2回 手に届きそうな三日月が空に浮かんでいる──Ry Cooder “Paradise and Lunch” 2022-12-07
- 第1回 きっと私たちが会うことはもうないだろう Allen Toussaint “Life, Love, and Faith” 2022-11-04
- 第16回(最終回) 「本物の詐欺を見せてやるぜ」@ジョン・ライドン 2022-07-04
- 第15回 文明化と道徳化のロックンロール 2022-06-10
- 第14回 ミスマッチにより青年は荒野を目指す 2022-06-02
- 10 もうひとつの現実世界――ポスト・トゥルース時代の共同幻想(後編) 2021-07-06
- 9 もうひとつの現実世界──ポスト・トゥルース時代の共同幻想(前編) 2021-05-03
- 8 あるいはハーシュノイズでいっぱいの未来 2020-05-05
第2回 かがやくばかり
やさしい夫がいて、かわいい子どもがいて、食卓には笑いがたえなくて。実家の両親はたのしく暮らしているし、おばあちゃんも気丈で元気だ。なのにどうしてこんなに不安で怖いのだろう。明日あの角を曲がると、奈落が待ち構えているのかもしれない……。誰も死んでほしくない。死なれたくない。なにげない日々の出来事から生の光と死の影が交錯する、おだやかで激しい日常の物語。
車で遠出した帰りのこと。いつの間にかとっぷり日も暮れて、へとへとである。なんとかアパートにたどり着いて車を停め、後ろのトランクを開けて買い込んだ荷物を取り出し、眠ってしまった子どもをチャイルドシートから抱き上げ、とそんなふうに夫と最後の力を振り絞ってテキパキ動いていると、どこからともなく「ピーー」とけたたましい音がする。もう辺りは完全に暗く、何も見えない。えっ、え?! とおろおろしていると、つづけて「プシュー」と空気砲のようなものが打ち上がる。後ろを振り返ると、隣の家の庭に設置されていた防犯装置が作動したらしい。半径何メートル以内にひとが侵入すると作動する、そういうシステムなのだろうか。こんなのいままで置いてなかったじゃん。お隣さん、最近になって防犯対策を見直したのだろうか。それにしても、庭からほぼ1メートルもない距離にアパートの駐車場があることを忘れないでほしい。とにかくめちゃくちゃびっくりした。
わたしはそのとき、これは「人生が終わった音」なのだと思った。ハイ! あなたの人生はここまでです、お疲れさまでしたー終了で〜す〜〜。本気で、そう告げられた音なのだと思った。それくらい不意打ちで、鋭く、そして避けがたい何かのようにそれは聞こえた。ほとんど茫然としながら「さっきの音まじでびっくりしたわ、人生終了のサイレンかと思った」と言うと、そんなわけないじゃん、と夫に笑われたが、それでもしばらく動悸がおさまらなかった。人生が終わるときって、あんな感じなんじゃないか。とにかく唐突で、予期せぬタイミングで。不条理で、そしてそれはとても、あっけらかんとしている。そこにはあかるささえ、ある。
ドラマ「ブラッシュアップライフ」のように、現世をやり直すことができるなら話は別だが、死んでもわたしたちは、バカリズムが退屈そうに腰掛けるあの真っ白い受付へたどり着くことはできない。来世の候補として、グアテマラ南東部のオオアリクイや、北海道のムラサキウニを提示されることもない。ドラマのなかでは、もしも次の人生でオオアリクイになるのが嫌なら、徳を積んで現世をやり直すことができる。大変だけどそれなら全然いいよな、と思う。いきおい腕まくりで今度こそ本番、という向きさえある。安藤サクラ演じる主人公の麻美が「じゃあもう一度現世をやり直します」と言って踵を返し、向かうその現世のドアの向こうは、毎度とてもまぶしかった。まぶしいならいいじゃないか、まぶしい世界なら、何度でもやり直したい。
朝、保育園に行くため自転車の前に子どもを乗せて走らせる、そのときの風と、ちょうど顎や鼻に触れる子どものあたまの清潔な匂い。鼻から大きく息をすってそれらを受け止めるとき、わたしには、いつか死ぬことがまるきり嘘のように感じられる。わたしにも子どもにも、それはあまりにもここから遠すぎる。死の気配すら、入り込む余地などない。だってわたしたちはいま、こうして守られているはずだから。
だれに? 何に? という声が聞こえる。いったいわたしや子どもはだれに守られているというのか。だれにも、何からも、ほんとうには守られてなんかいない。こんなにも剥き出しで、やわらかく、命を覆うものなど存在しない。そしてそれは、自分に限ったことではない。気づけばみんな、あまりにも無防備に、それぞれの生をこの世界に晒しているではないか。
死んだらどうなるのか、だれもそのことを知らずに、いつ死ぬのかなんてほとんどわからずに、昨晩の残りものをレンジで温めて無表情のまま口へ運び、皿を洗い、ため息をつき、また眠りにつく。たまにこころを動かされることもある。たとえば、あまりにうつくしい夕日にあっけにとられる。思わず写真を撮ってみる。けれどカメラに収まったそれは、目の前の景色とは全然違う。こんなに眼前に大きくひろがる太陽は画面のなかに縮こまり、それはどこにでもある退屈な一枚にすり変わる。帰り道をとぼとぼ歩く。こころを動かされても、つまらなくても、でもやっぱり死はここにいない。そんなことすら、じっさいには考えない。なんとなく不安になって、きょろきょろと周りを見渡す。車通りは多いが、歩道を歩くひとは自分以外にいない。
たまに笑う。ごくまれに泣く。静かに泣く。だれかの前で隠すことなく、声をあげて泣いたのはいつだっただろう。ひとの声がする。風が鳴る。まどろみのなかで、ここがどこだかわからなくなるときが一番、深く息を吸い込むことができる。あの夜、暗闇のなかで出し抜けに響いた警告音。こわかったなあ。でもやっぱりあれはただの生活の音だった。誰かのための、生活の音。こわかったー、と言って笑ってそれで済んだのだ。ああ、よかった。でも次はいつだろう?
死にたくない、とこれまで自分はずっと死を恐れているのだと思っていたが、そうではないのかもしれない。死が遠い。というより、その遠近感がわからない。もしかすると、わたしはそのことがずっとこわいのかもしれない。死を感じられない、そのこと自体が。だから、深刻な病気をすぐに疑ってしまう。そうであるかもしれないと思うことで、死をこちらへたぐり寄せて、なんとかその匂いをすこしでも嗅ごうとする。同様に、近しいひとの死を極度に恐れるのも、落差にショックを受けないようにする予防線のようなものかもしれない。
対して夫は、カレンダーを見るたびに「もう今月も半分過ぎたよ。あー死に近づいちゃった」とか、誕生日を迎えれば「やだな。また死が近くなった……」など、ことあるごとに(自分が)死に、あるいは死が(自分に)近づいた、と言う。けれどそこにそれほどのリアルな感触は伴っていないように見える。
「死んだらさぁ、なにがイヤってものすごい暇じゃん」と夫はつづける。死んだら暇なのか。暇さえ感じられないのが死なのではないか、と反論するが、夫にとってそうではなく死はとにかく暇、であるらしい。
わたしたちなんて、みんな元々ここにはいなかったんだから、と思う。なにも無いところから生まれてきて、自由に、いやとても不随意に、もがきつづけて知らないうちにまた無へと還ってゆく。はじまりも終わりも、そこに意味など本来はなく、ただ生も死も不条理である。その、星のため息のような瞬間が、ほんのわずかに宇宙をかがやかせるだけではないか。
宇宙とか持ち出さないでほしい、と夫は言う。宇宙に立ってなにかを思ったり、眺めたりするわけではないのだから。まあそれはそうなんだけど。SFってなんなんだよ、って話だよね。サイエンスフィクションって、宇宙がそもそも、めちゃくちゃフィクショナルじゃん。「宇宙」が存在することが変すぎる。というか宇宙がなければわたしたちも存在しないという、その前提がまず理解できない。この空の向こうに、無限のそれがひろがって、そのどこまでもある奥行きのあちこちにばかみたいにでかい星が浮かんでいる。なんだそれ、こわすぎない? でもすべてフィクションではなく、ばかでかい星もブラックホールも無重力も、どこかにある。月も太陽も、ちゃんと存在するから朝があって夜がある。そう、重力だって、考えたらまじで謎すぎるよね、と言うとまあたしかにね、と返される。宇宙って、笑ってしまうほどによくわからない。あれ、死の話してたんじゃなかったっけ。夫はいつの間にか、もう眠っている。読書灯を消して、わたしも目を閉じる。
*
久しぶりに夕方にひとりで家を出て、友人たちと遅くまで飲んで帰った夜のこと。みんなで二軒目の居酒屋を目指す道すがら、夜道を一列になって歩いていた。こんなに暗かったっけ?! と口々に言う。ふだんみな移動は車だし、夜道を歩くことはほとんどない。そしてなにより、地方には街灯が少ない。真っ暗ななかを黙々と歩きながら、ひとりが「うおおおああ!!」と叫び、どうやら深めの側溝に落ちたらしい。大丈夫?! と声をかけるも、とにかく暗くて彼が側溝に落ちたことさえわからない。大丈夫、と言いながらそのひとはなんとか側溝から這い上がるが、しばらく膝を庇って歩いているように見えた。大人が足を踏み外すくらい、田舎の夜は暗い。慎重に、また一列になってちいさな居酒屋を目指しながら歩いた。
二軒目で大いに飲んだ後、手を振って別れ、今度はひとりの夜道を歩く。見上げれば、夜空の星々の隙間を飛行機の光はどんどん切り裂き、それは平面のただつまらない絵画を見ているようで感慨がない。わたしの目には夜空はいつも平面である。
酔っ払っているらか、横目で通り過ぎる自分より背の高いブロック塀を、なぜかかんたんに乗り越えられるような気がする。と思っててっぺんに手をかけてみると、とてもざらざらして痛い。こんなところに登ったところでどうにもならない。民家だし。でも、酔った日にはこのちいさな半径のなかではなんでもできるようなおおきな気持ちになって、けれどなったところでなんなのか。なぜかさっきから太ももの辺りが痒くてたまらず、でも厚手のジーパン越しに掻いてもなんの手ごたえもない。それでバシバシ太ももを叩く。叩いていたら愉快になってきて、かんたんにいい夜だな、と思う。トートバッグをぶんぶん振ると、なかでお菓子の箱が揺れる。夕方、集合時間まですこし時間があったので、すぐそばの洋菓子屋でちょっとした焼き菓子の詰め合わせを買った。ふと、いまは遠くに住む友人に送ろうと思ったのだった。あの店すごく好きだったんです、とこの前電話で話したときに言っていたから。それがトートバッグのなかで揺れている。パイやクッキーが割れないといいが、気がおおきいので割れるはずなんかない、と思っている。
夫が「死が近づいた」と言うたびに、わたしは「でも裏がえせばそれって、いまが一番死から遠いってことだよ」と返す。いつ来るかわからぬそれを受け身で待つならば、いつだっていまがいちばん死から遠いはず。でも、それはそう思い込んでいるだけだ。遠いと思っていても、ほんとうには息をひそめてそれは、いまも至近距離にいるのかもしれない。真っ暗で見えないだけで。ほんとうには遠いのではない。ただ、その遠近感がわからないだけ。それにしても、とにかく道が暗い。もうすぐ踏切がある。子どもはもうとっくに寝ただろう。田舎の夜道を歩くひとは、自分のほかにいない。田舎って星がよく見えるんだろうね、とこちらに引っ越す前に夫と話していたことを思い出すが、地方に対する認識が雑すぎる。だってここからも、星はあまり見えない。辺りは真っ暗なはずなのに、星の見え方は東京とさほど変わらない。
死んだって、かがやきすらしないのではないか。死んだら星になるだなんて、そんなつまらないこと、言わないでほしい。もしも光ってたって、わかるはずなどない。いま、意味もなくここにいる。だれにも見つけられずに、ここにいる。だれにも守られずに、存在する。星は見えない代わりに、蛙の声が聞こえている。東京ではさすがに蛙は見なかったな、と思う。勤め先の学校で、生徒が「田舎のなにがいやって、カエルですよ。うちのまわり田んぼばっかでほんと夜うるさいんです」と言っていたことを思い出す。蛙のぐるるる、という声を聞きながら、もうしばらくの帰路をゆく。